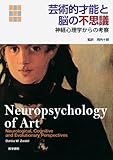![]() わたしの中にいる他人。心の中に別の人がいる。存在を感じるだけでなく、完全に第三者的な思考を持っていて、友人のように会話することもできる。
わたしの中にいる他人。心の中に別の人がいる。存在を感じるだけでなく、完全に第三者的な思考を持っていて、友人のように会話することもできる。
そのような感覚を感じることがありますか?
ある人たちは、そのような話を聞くと、何か病的な印象を受けるかもしれません。おそらく、頭の中に声が聞こえるという統合失調症や、心が多くの別人に分かれる多重人格、すなわち解離性同一性障害(DID)を思い浮かべるのでしょう。
しかし、「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() という本で、そうした病気を専門とする大饗(おおあえ)広之先生ははっきりと、次のように述べています。
という本で、そうした病気を専門とする大饗(おおあえ)広之先生ははっきりと、次のように述べています。
たとえば「頭のなかにもう一人の自分がいる」と訴える人がいても、もはやわれわれは彼をすぐさま病的と決めつけるわけにはいかない。
彼らに統合失調症や多重人格などという診断は当てはまらないし、それどころか、その訴えをすぐに「症状」とみなすことさえできない。
信じられないかもしれないが、そういった軽微な人格の複数化が潜在的にはかなりの勢いで拡がっているのである。(p3)
ここでは、そうした現象は、必ずしも「病的」ではなく、統合失調症や多重人格の診断は当てはまらず、むしろ意外なほど多くの人が経験しているかもしれない、と書かれています。
この現象は医学的にはイマジナリーコンパニオン(IC:想像上の仲間)、より日常的にはイマジナリーフレンド(IF:空想の友だち)と呼ばれる現象で、いまだ多くの謎に包まれています。
このブログでは、1年半前に、IFについての詳しい考察を書きました。当時は、わたしの知識の及ぶ範囲としては、書けることはすべて網羅したと考えていました。
しかしそれ以降読んだ多くの本、たとえば先ほど挙げた大饗広之先生の「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() や、岡野憲一郎先生の解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合
や、岡野憲一郎先生の解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() 、アリソン・ゴプニック先生の哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)などを通して、より理解が深まったので、改めて考察をまとめることにしました。
、アリソン・ゴプニック先生の哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)などを通して、より理解が深まったので、改めて考察をまとめることにしました。
こうした軽微な人格の多重化の原因は何なのでしょぅか。本当に病的でないとみなしても大丈夫なのでしょうか。解離性障害や発達障害との関わりはあるのでしょうか。4つの観点から考えてみたいと思います。
さまざまな「わたしの中の他人」を結び合わせる
「心の中に別の人間がいる」。
そんなことを言おうものなら、冗談とみなされたり、心の健康を疑われたりするかもしれません。見えない友達がいる、というのは、世の中の大半の人にとって、お世辞にも良い印象を与えるものではありません。
しかし、これまでこのブログで何度も扱ってきたとおり、「心の中に別の人間がいる」というのは、意外にも、さほど珍しい現象ではありません。
たとえば以下のような例を考えてみてください。
■子どもの空想の友だち イマジナリーコンパニオン(IC) 幼い子どもの半数近くが空想の友だち(イマジナリーコンパニオン)を持つことが知られています。子どもの空想の友だちは、健全な成長の過程で、見えない遊び友だちとして一時的に現れ、いつの間にか消えてしまいます。
![子どもにしか見えない空想の友達? イマジナリーフレンドの7つの特徴に関する日本の研究 | いつも空が見えるから]()
■サードマン現象
特殊な条件下でみられる「サードマン現象」は、雪山などで遭難したとき、そばに「もう一人のだれか」がいる気配を感じ、励ます声を聞きながら、生還した人たちのエピソードによって一躍有名になりました。
![サードマン・イマジナリーフレンドが現れる5つの条件―「いつもきみのそばを歩くもう一人がいる」 | いつも空が見えるから]()
■解離性同一性障害(DID)
重い病気とみなされている、解離性同一性障害(DID)、いわゆる多重人格もまた、心の中に大勢の他人が現れます。子どもの空想の友だちと違って、人格交代して意識をのっとり、ときに攻撃的だったり、トラウマチックだったりすることが特徴です。
![多重人格の原因がよくわかる7つのたとえ話と治療法―解離性同一性障害(DID)とは何か | いつも空が見えるから]()
そのほか、トランス性の憑依現象や、睡眠中に別人のように行動するノンレムパラソムニアなども周辺の現象と思われますが、ここでは複雑になるので割愛します。
これらの現象は、見ての通り、まったくの健康とみなされているものから、病的とされているものまで様々であり、それぞれ別々の分野の専門家によって研究されてきた歴史があります。
子どものICは発達心理学者たちにより、DIDは精神科医たちによって、そして、サードマン現象は、ときに宗教家や神学者たち、そして近年では神経科学者たちによってメカニズムが究明されています。
ところが、不思議なことに、これら複数の「わたしの中の他人」現象につながりがあるのか、ということに関しては、それぞれの専門分野を超える具体的な研究は、ほとんどなされてきませんでした。
青年期のイマジナリーフレンドの不可思議さ
さらに、「わたしの中の他人」には、もう一つ、忘れてはならない、規模の大きな集団があります。
それはすなわち、この記事でおもに扱う、青年期のイマジナリーフレンドのことです。
ファンタジーと現実 (認識と文化)によると、1991年の日本の調査では、約2.8%の人が大学生になってもイマジナリーフレンドを持っていることがわかりました。(p125)
代表的な精神疾患である統合失調症でも、有病率は人口の約1%ほどと言われていますから、その3倍近くを数える青年期のイマジナリーフレンドが、その規模の大きさに反して、いかに見過ごされてきたかがわかります。
「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() の中で、解離性障害に詳しい精神科医の大饗広之先生は、そのことを率直にこう認めています。
の中で、解離性障害に詳しい精神科医の大饗広之先生は、そのことを率直にこう認めています。
精神科臨床の現場でICが認識されるようになったのは、まだここ最近のことである。
しかし、注意を向ければ向けるほど、こうした現象が青年のあいだに(病的か健全かを問わず)広く蔓延していることに気づかざるを得ない。(p183)
青年期のIC、つまりイマジナリーフレンドは、子どもの空想の友だち研究や、病的なDIDの研究から長く取り残されてきました。
時折、それぞれの分野の専門家が、関連性に言及していますが、その意見はまとまりを欠いているように思えます。たとえば次のような意見が聞かれるかもしれません。
■子どものイマジナリーコンパニオンはまったく健康なもので、解離性障害や発達障害と無関係
■青年期のイマジナリーコンパニオンは解離性障害やアスペルガー症候群との関連が示唆され、病的なものとなる場合もある。
■イマジナリーコンパニオンが記憶の消失を伴わないのに対し、解離性同一性障害(多重人格)の交代人格は、人格同士の間で記憶のやりとりができないので、両者は別物
こうした意見からすると、あたかも、青年期のイマジナリーフレンドは、子どもの健康なイマジナリーフレンドとも、病気としての解離性同一性障害(DID)の交代人格とも性質をたがえる謎めいた現象であるかのように思えます。
これらは互いにつながりのない、別のメカニズムによって生じる、異なる現象なのでしょうか。
青年期のイマジナリーフレンドは、「わたしの中に他人がいる」という明確な共通点があるにもかかわらず、健康な子どもの空想の友だちとも、病的な多重人格とも成り立ちを異にする独特な現象なのでしょうか。
すべては根底でつながっている
わたしは、このブログで、1年半ほど前、イマジナリーフレンドとは何か、という4つの考察をまとめた以下の記事を書きました。
![イマジナリーフレンド(IF) 実在する特別な存在をめぐる4つの考察 | いつも空が見えるから]()
そのころ様々な分野に点在する「私の中の他人」の現象すべては、おそらくつながりがあるのだろうとは思っていたものの、うまく関係を整理しきれなかったため、あくまで4つの観点から掘り下げるにとどめました。
しかし、それから1年半が経ち、様々な書籍を読んできた結果、4つの観点から掘り下げた先は、確かに奥の方で一つに つながっていることに気づきました。
それぞれの現象の根底にあるメカニズムは、ちょうど虹色のグラデーションのように連続性を持つものであり、その場その場によって、さまざまな形をとって表に現れているにすぎないのです。
これは、多くの子どもが持つ空想の友だちが、解離性同一性障害につながりかねない病的なものだとか、危険な要素を持っている、という意味ではありません。 おいおい説明しますが、どちらかというとその逆です。
1年半前の考察の4つの観点とは、以下のようなものでした。
1.発達心理学
2.解離
3.愛着理論
4.アスペルガー症候群
これらの方向性は、幸いにもすべて正しかったようです。
それで、今回のさらなる4つの考察では、前回の4つの観点をさらに掘り下げ、根底のところでそれらが一つにつながっていることを説明したいと思います。
この解説は、前回の記事を土台としているので、イマジナリーフレンドについての基本的な説明をお知りになりたい場合は、イマジナリーフレンド(IF) 実在する特別な存在をめぐる4つの考察 も合わせてご覧になるようお勧めします。
このたびも、様々な書籍から引用した長文で、おそらくこれまでのわたしの記事の中で最長なので、気楽に読んでいただくのは難しいと思います。しかし、この分野に関心のある方は、辛抱強く最後までお付き合いいただければ幸いです。
もちろん、前回同様、専門家ではない一個人の考察にすぎないこともお含み置きいただければ嬉しく思います。
第一章 「心の理論」が生み出すIF
まず、最初のセクションでは、発達心理学の研究に軸足を置きつつ、多くの子どもたちに見られるIFと、青年期のIFとの関連性を考えます。
幼年期の子どもに見られる無邪気なIFと、青年期に見られるIFとの間につながりはあるのでしょうか。
子どものIFは、各統計で割合に差がありますが、かなりの数の子どもが、2-3歳から7-8歳ごろまでの期間に、想像上友だちを一時的に創りだすと言われています。
たとえば解離性障害―「うしろに誰かいる」の精神病理 (ちくま新書)![]() にはこうあります。
にはこうあります。
一般人の20-30%にみられ、一人っ子か第一子の女性に多いとされる。8-12歳の間にはかなり少なくなってしまう。(p128)
一方で、哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)には、もっと割合の高い統計が紹介されています。
テイラーは、三、四歳児とその親を無作為に選び、空想の友だちについて具体的に質問していきました。
すると、子どもたちの大多数、実に63パーセントもが、生き生きとした、ときに不気味な空想の友だちをもっていることがわかりました。(p74)
こうした調査からすると、おそらくは半数近い子ども、つまり3人に1人から、2人に1人ほどの割合の人が、子ども時代には空想の友だちとの交流を楽しんでいるのでしょう。
多くの人はそのことを覚えていませんが、統計は、IFが子どもたちの間にごく普通に生じる普遍的な現象であることを物語っています。
当然ながら、それほどありふれた現象が、心の病気と関係しているとは思えません。現に、上記のテイラー博士の別の研究結果について、おさなごころを科学する: 進化する幼児観にはこう書かれています。
この研究領域の第一人者であるテイラー博士の研究からも、児童期における空想の友達の有無は、青年期における精神疾患とは関連がないことが示されています。(p141)
それで、まずはっきりと断言しておきますが、これまで何度も書いてきたとおり、子どものIFは基本的に言って精神疾患との関係は何らありません。
ですから、親は我が子がIFを持っていることに気づいた場合、心配したりするのではなく、むしろ子どもと一緒に空想の世界の冒険を楽しむことができます。
キーワードは「心の理論」
しかし、子どものIFが精神疾患とは関係がないからといって、子どものIFと大人のIF、はたまたDIDとの間にまったくつながりがない、というわけではありません。
わかりやすくするために別の例で考えてみましょう。
たとえば、真面目であることは、それそのものが、将来の病気と関係することはないでしょう。むしろ真面目であることは良い結果をもたらします。
しかしあまりに真面目さの度が過ぎて、完璧主義的になってしまうなら、それは様々なストレスを抱え、心身の病気を呼びこむ可能性をはらんでいるかもしれません。
同様に、IFを持つ子どもは、研究によるとある性格特性を持っていることがわかっています。それそのものは決して悪いものではなく、むしろ優れた能力といえます。
しかし、その性格特性が強すぎる場合、子どもは単にIFを持ちやすいだけでなく、あたかも真面目さが行き過ぎた完璧主義の場合のように、心身に大きなストレスを抱え込むことになってしまいます。
その行き過ぎたある性格特性の結果が、青年期のIFであり、さらにはDIDであると考えられます。
ではその性格特性とはなんでしょうか。おさなごころを科学する: 進化する幼児観には、IFを持つ子どもが次のような特徴を示すと書かれています。
空想の友達を持つ幼児は、他者の視点を考慮する能力に長けていること、より複雑な構造を持った発話ができること、知識状態の理解に優れていること、などが示されています。(p253)
ここでは、IFを持つ子どもは、「他者の視点を考慮する能力」や複雑な会話の能力に秀でていると書かれています。
これを、哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)によると、次のような一つの言葉で言い換えることができます。
空想の友だちのいる子はそうでない子より心の理論が発達している傾向はあります。空想の友だちのいる子はいない子よりも他人の思考、感情、行動の予測が上手です。(p88)
そうです、IFを持つ子どもは、他の子どもよりも、他人の思考や感情、行動を汲み取る力、すなわち「心の理論」が優れているのです。
「いない人」のことまで考える
「心の理論」が優れている、というのは、一見して、とても良いことのように思えます。実際にところ、それはすばらしい才能です。
現代社会では、しばしば、空気の読めない人がKYと揶揄されます。空気を読む力は、有能な社会人になる上で、とても大切だと考えられています。
「心の理論」が優れている人は、他の人の気持ちがよくわかるので、適切なときに空気を読むことができますし、優しい気遣いや気配りが得意です。
他の人の心に深い興味と関心を持っているので、周りの人に深く感情移入することができ、とても温かみのある人に成長することもあります。
それで、哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)には、「心の理論」が優れ、IFを持つ子どもについてこう書かれています。
また、これは通説とあべこべなのですが、人なつっこい子のほうが、内気で孤独な子より空想の友だちをもちやすいそうです。
…空想の友だちのいる子は周囲の人たちのことを人一倍気にするので、「いない人」のことまで考えてしまうのかもしれません。(p88)
内気な子どもではなく、他の人に積極的な関心を向ける気配りのできる子どもだからこそ、「いない人」のことまで考えてしまい、イマジナリーフレンドを創造することができます。
単に他の人に興味があるだけでなく、「心の理論」が優れているため、自分以外の人の気持ちに敏感で、相手の立場に立って、どんな気持ちなのか具体的に想像することができます。
その結果、現実に存在する他人だけでなく、現実に「いない人」の気持ちまで手に取るよう想像できてしまいます。そうして創られるのが、架空の目に見えない友だち、イマジナリーフレンドなのです。
子どものイマジナリーフレンドは、このような社交的で、他の人の気持ちを考える能力の高い子どもが、親が下の子の世話などで忙しくなったりして、寂しく感じたときに創りだすことが多いと言われています。
おさなごころを科学する: 進化する幼児観によると、ほかの研究でも、IFを持つ子どもは、無生物やランダムな図形の動きに生き物らしさを感じることができたり、他の子どものIFにも感情移入できたりすることがわかっています。
いずれの研究結果も、IFを持つ子どもが、まわりの人の気持ちをよく汲み取り、時には物や「いない人」にまで感情移入してしまうことを示しています。
小説家としての才能
このような幼いころの優れた「心の理論」は、何も子どものころだけの才能ではありません。
学生のころも、また大人になってからも、優れた才能として開花する可能性があります。
哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)によると、先ほどのテイラー博士は、IFを持つ子どもたちの中には、後に創造的な才能を開花させる人が含まれている、ということに気づきました。
マージョリー・テイラーは、子どもが空想の人物を生み出す能力と、大人が反事実からできている架空の世界を創作する能力、つまり小説家や劇作家、シナリオライター、役者、映画監督がもつような能力には関連性があることに気づきました。(p92)
テイラーが注目したのは、作家や役者の能力と、子どもの創りだすIFの類似性です。
IFを持つ子どもは、「いない人」の気持ちまで想像してしまいますが、それは小説家や俳優には必須の能力です。
小説家やシナリオライターは、現実には存在しない登場人物の心の動きを理解して、リアルな文章を書かなければなりませんし、俳優は存在しない人物の気持ちを理解して役になりきらなれければなりません。
このような想像力は、普通の人にはなかなか備わっていないものですが、子どものときにIFを創造していた人の場合は、そのときの能力が、そのまま活かされる場合があります。
続く部分では、テイラー博士の具体的な調査が紹介されています。
テイラーは文学賞を受けた作家から熱心なアマチュアまで、小説家を自認する50人について調査を行いました。するとほぼ全員が、作品の登場人物の自律性を認めていました。
…興味深いのは、約半数は幼児期の空想の友だちを覚えていて、その特徴もいくらか答えられたことです。
対照的なのは一般の高校生で、幼い頃は多くが空想の友だちをもっていたのでしょうが、今もそれを覚えていると答えた生徒はわずかでした。(p93)
テイラー博士は、小説家たちを集めて、空想の友だちと、小説のキャラクターについて、アンケートをとりました。
すると、IFと小説のキャラクターには、どちらも自分の意志をもって動くという類似点があり、しかも小説家の半数が子どものころのIFを覚えていたのです。
これは、子ども時代のIFと、小説の創作の両方に、「いない人」の気持ちまでありありと想像する類まれな「心の理論」が関わっていることを示しています。
もちろん、IFを持つ子どもが人口の1/3から1/2ほどいるとはいえ、そのすべてが後に作家や俳優になるわけではありません。
IFを持つ子どもたちは、全体として平均すれば、IFを持たない子どもたちより「心の理論」が優れているのは確かです。
しかしIFを持つ子どもたちの中だけを比べてみると、ほんの少し「心の理論」が優れているだけの子どももいれば、「心の理論」が飛び抜けて優れている子どもも、わずかながらいることでしょう。
そうした飛び抜けて優れた「心の理論」と、そのほかの様々な環境要素や才能とが運良くマッチした場合に、将来、小説家や俳優になる子どもが現れるかもしれません。
このように書くと、「心の理論」は優れていれば優れているほど良いかのように思えます。しかし、必ずしもそうではありません。
行き過ぎた真面目さが身を蝕むように、行き過ぎた「心の理論」もまた、両刃の剣となりかねません。
小説家や詩人はなぜ気分障害を抱えやすいのか
天才の脳科学―創造性はいかに創られるか![]() という本では、優れた芸術的才能を持つ作家たちについて、統計的な調査が行われています。
という本では、優れた芸術的才能を持つ作家たちについて、統計的な調査が行われています。
すると、彼らは優れた才能だけでなく、精神的な脆弱性も持ち合わせていることが明らかになりました。
これらの英国の優れた文系の人々は、非常に高い頻度で気分障害に陥っている。
全例の38パーセント以上が感情障害で治療を受けたことがあり、なかでも劇作家がもっとも頻度が高く、その次が詩人だった。(p143)
この研究では、英国の優れた詩人、劇作家、小説家などが調査されましたが、彼らはかなりの割合で気分障害を抱えていました。
有名なところでは、ハリー・ポッターの作家J・K・ローリングが、有名になる前、うつ病で生活保護を受けながら小説を書いていたエピソードが知られています。
興味深いことに、これら小説家や詩人に多かった病気は、一般に天才的な才能との関係が取り沙汰される統合失調症ではありませんでした。
作家の面接を始めて一連の精神測定検査を行っていくと、私の仮説の誤りがすぐに明らかになってきた。
意外なことに作家の多くが、双極性障害か単極性鬱病に合った気分障害の個人歴があり、治療を受けたことがあった。(p139)
これに対し、芸術的な分野ではなく、科学的な分野の天才たちに目を向けると、統合失調症の不全型や、家族に統合失調症の患者がいる例がしばしば見られるそうです。(p144)
ではなぜ、科学の分野には統合失調症の天才が多い一方で、芸術の分野には気分障害の天才が多いのでしょうか。
日本の有名作家を見ても、夏目漱石、太宰治、三島由紀夫、川端康成など、気分障害に悩まされた有名作家には事欠きませんが、そこには何が関係しているのでしょうか。
端的に言えば、科学の分野で成功するのと、芸術の分野で成功するのとでは、求められる能力が異なっているのです。
科学の分野では、鋭いひらめきと洞察、論理的で精密な思考が求められます。
これはアスペルガー症候群の人などが得意とする分野であり、近年の研究によると、アスペルガー症候群と統合失調症の脳の活動は類似していて、何らかの共通要因があるとみなされています。
![脳MRI画像で自閉スペクトラム症を85%判別―ADHDやうつ病ではなく統合失調症と脳活動が類似 | いつも空が見えるから]()
それに対して、小説家や詩人に必要なのは、データを読み取るロジカルな思考でも、統合失調症の妄想じみた独創的なひらめきでもありません。
芸術に必要なのは感性、特に人の心を読み解く力「心の理論」なのです。
先ほど、行き過ぎた「心の理論」は両刃の剣になると書きました。容易に想像がつくことですが、他の人の気持ちがわかるだけでなく、わかりすぎてしまうことは、大きなストレスになるでしょう。
優れた「心の理論」はこまやかな作品を生み出しますが、同時に人の表情の裏にある感情が読みすぎてしまったり、周囲の人たちの評価に敏感になりすぎてしまったりして、疲れてしまう原因にもなるでしょう。
しかしながら、根底にある問題は、そう単純ではありません。「心の理論」が優れているから、気分障害になりやすい、というのは、問題の本質を見落としている因果関係の錯誤です。
「心の理論」が優れていること自体は何も問題はないのです。「心の理論」が優れ、IFを生み出した子どもたちの多くが心の問題を抱えなかったことがそれを示しています。
要点はここです。
もし、その優れた「心の理論」が、人への純粋な興味から育まれたものなのであれば、そこには何の問題もありません。
しかしもし、その優れた「心の理論」が、生きるために強いられて発達させた適応だとしたら?
セクション2では、いよいよ発達心理学が描き出す子どものイマジナリーフレンドと、青年期のイマジナリーフレンドとがリンクすることになります。
第二章 「愛着トラウマ」を癒やすIF
セクション1で考えたのは、子どものイマジナリーフレンドを生み出す要因の一つが、優れた「心の理論」、つまり他の人の気持ちを汲み取る能力である、ということでした。
そして、そのような優れた「心の理論」は、小説家や詩人などの芸術的才能とも関係していますが、不穏なことに彼らは気分障害を高い確率でもちあわせている、ということを考えました。
しかしながら、それら小説家や詩人が持つ気分障害を、うつ病や双極性障害などと結びつけるのは、いささか的外れかもしれません。
なぜなら、それらの芸術的な作家たちが持つ気分障害の原因は、一般的な意味でのうつ病や双極性障害ではなかったと考えられるからです。
彼らが優れた「心の理論」を育て、芸術的才能に秀で、しかも気分障害を抱えていた。そのすべてを説明できるのは、うつ病でも双極性障害でもなく、「愛着トラウマ」です。
「愛着トラウマ」とは何か
「愛着トラウマ」とは何でしょうか。
ここは誤解を招きやすい点なので、しっかりと理解していただきたい部分ですが、「愛着トラウマ」は、その語感から連想されるような、激しい児童虐待ではありません。
ややこしく感じるかもしれませんが、「愛着トラウマ」とは、「トラウマ」という名前がついていながら、衝撃的な体験どころか、本人も家族もまったく気づいていないような経験を指しています。
以前の記事で説明したとおり、ここでいう「愛着」とは、英国の精神科医、ジョン・ボウルビィが提唱した愛着理論に関するものです。
![長引く病気の陰にある「愛着障害 子ども時代を引きずる人々」 | いつも空が見えるから]()
愛着理論は、ごく幼いころ、生後半年から1歳半くらいまでの養育者の関わり方が、その後の人生における対人関係や思考パターンの型となる、という考え方です。
後ほど説明しますが、現在では、これは単なる理論ではなく、生物学的な現象であることが、脳科学の研究などで裏づけられています。
「愛着トラウマ」というと、さぞかしひどい親のもとで悲惨な育てられ方をした子どもに当てはまるのだろうと思いがちですが、それは全くの誤解です。
むしろ非常に優しい親の元で育ったとしても「愛着トラウマ」を抱える場合があります。
そのことをわかりやすく説明している、母という病 (ポプラ新書)![]() の説明を見てみましょう。
の説明を見てみましょう。
基本的安心感は、ゼロ歳から、1,2歳までの間の、まったく記憶にも残らない体験によって形づくられる。
…この時期に、母親からの全面的な関心と愛情を受けて育った人は幸運だと言える。
しかし、不幸にもそうでなかった場合、子どもは、基本的安心感を育むことができず、いつも居心地の悪さを感じ、自分に対しても違和感を覚えることになる。
自分が自分であって自分でないような不全感をもって育つことになりやすい。(p74-75)
ここにある「基本的安心感」とは、自分以外の他人は、基本的にいって信頼に価するものなのだ、という無意識の感覚のことです。「基本的信頼感」が、つまり「愛着」というものの一面なのだ、と言い換えることができます。
「基本的信頼感」がちゃんと備わっている人は、他の人を道理にかなった仕方で信頼することができますが、もしこれが欠けていたら、その後の人生で、心の底から他人を信頼して自分を委ねることを、たとえ頭では安全だとわかっている相手に対してでさえ難しく感じます。
さらにいえば、人を信じるというのがどういうことなのか、本当の意味で理解することができません。
これはちょうど、子どものときに言語を学ぶかどうか、というシチュエーションに置き換えてみればわかりやすいでしょう。
言語も愛着も学習の臨界期、また感受性と呼ばれる期間があります。子どものときに慣れ親しんでいれば、ネイテイブとして自由に言語を操れますが、その時期を逃すと、後から学んでも、本当の意味で母語のように自由に扱うことはできないのです。
「基本的信頼感」つまり、愛着もそれと同じです。
母親との絆は、いつでも育まれるわけではない。生まれてから一歳半までの限られた時間しか、安定した絆は形成されないのだ。それは、子どもの脳でオキシトシンなどの受容体が、もっとも増える時期でもある。
その限られた時間は、母子双方にとって、かけがえのない特別な時間だ。そのときを過ぎてしまってから、いくら可愛がったところで、もう間に合わない。不可能ではないが、その時間を取り戻すことは容易ではない。(p76)
ここに書かれている、母親との絆を限られた期間に育めなかった状態、それこそが「基本的信頼感」の欠如であり、「愛着トラウマ」です。
「愛着トラウマ」を抱える子どもの中には、虐待やネグレクトに遭った子どもも当然含まれますが、それ以外にも、やむを得ない事情で、この時期の絆の形成に失敗してしまうケースはいくらでも考えられます。
たとえば、親との死別、たまたま親が産後うつなどで子どもをじっくり育てられなかった、仕事が忙しくて母親以外が交代で面倒を見ていたなど、親が悪いとは到底言えないケースも多々あるでしょう。
しかし先ほど書かれていたとおり、いかなる事情があるとしても、その時期を逃せば、後でいくら愛情を注いでも手遅れで、子どもは「愛着トラウマ」を抱えたまま成長することになります。
![誰も信じられない、安心できる居場所がない「基本的信頼感」を得られなかった人たち | いつも空が見えるから]()
幼いころに学ぶ感情のパターン
それにしても、「愛着トラウマ」を抱えると、いったい子どもの身に何が生じるのでしょうか。
少し難しいですが、その時期に、幼い赤ちゃんの頭のなかで、何が起こっているのかをかいま見ることにしましょう。
解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() には、「愛着トラウマ」の形成がどのように起こるのかが、次のように書かれています。
には、「愛着トラウマ」の形成がどのように起こるのかが、次のように書かれています。
幼児は幼いころに母親を通して、その情緒反応を自分の中に取り込んでいく。
それはより具体的には、母親の特に右脳の皮質辺縁系のニューロンの発火パターンが取り入れられる、ということである。
…そしてこれは、ストレスへの反応が世代間伝達を受けるということなのだ。そこに解離様の反応の世代間伝達も含まれる、(p17-18)
少しわかりにくいかもしれませんが、簡単に言えば、生後まもないその時期に、赤ちゃんは養育者の情緒反応のパターンを、自分の脳に取り込む、ということです。
もっとわかりやすくいうと、感情のパターンが親に似る、と言い換えることができるでしょう。
赤ちゃんは、生後半年から1年半ほどのその時期に、生涯にわたる、感情反応の土台となるパターンを、親から読みとることで脳に刻み込みます。以降の人生の感情や思考は、そのパターンに基づいて積み上げていくことになります。
では、たまたまその時期、母親が精神的に不安定で混乱していたならどうなるでしょうか? 母親にとってはその混乱は一時的なものかもしれませんが、子どもはその混乱を土台として取り込んで脳を成長させていきます。
もし虐待されたり、養育者がコロコロ変わったりすればどうでしょうか。やはり普通とは違った異常なパターンが組み込まれることでしょう。
もちろん、ちょっとした育て方のミスが命取りになるというほど、赤ちゃんの脳は柔軟性に欠けるわけではありません。幼いころに言語を学習する機会を逃しても、まだ10代のころまでに学習し始めるなら、ある程度は取り戻せるかもしれません。愛着も、ある程度はフォローアップできます。
しかしそれでも、幼いころに混乱した養育環境にさらされると、その影響は、脳の発火パターンとして、その後の人生に根深い影響を与えます。
空気を読み過ぎる「過剰同調性」
そのような幼いころに学んだ混乱した感情のパターンが現れる結果の一つが、「過剰同調性」と知られている性格特性です。
ようやくここで、1つ目のセクションで考えた話と結びつきます。
「過剰同調性」とは、言い換えると、空気を読みすぎ、相手に合わせすぎる傾向、すなわち、異常発達した「心の理論」なのです。
「過剰同調性」は以前の記事で取り上げたとおり、解離性障害の患者の素因として知られています。
![空気を読みすぎて疲れ果てる人たち「過剰同調性」とは何か | いつも空が見えるから]()
解離の構造―私の変容と“むすび”の治療論![]() で解離性障害の専門家の柴山雅俊先生は、「過剰同調性」についてこう述べていました。
で解離性障害の専門家の柴山雅俊先生は、「過剰同調性」についてこう述べていました。
嫌われないように相手に合わせる。相手が喋っている内容から、その人の考え方を読み取って、それをもとにしてその人が好むようなことをいう。嫌われるのも、怒らせるのも、議論になるのも怖い。(p139)
つまり家族の雰囲気や学校という場での緊張感、雰囲気、空気などを読んで、トラブルにならないように自己犠牲的に周囲に合わせようとする。
以上のような特徴を「過剰同調性」と名づける。(p83)
相手の考え方を過剰に読み取って、それに合わせていく、空気が読めないKYとはまさに対極にある特性であることがわかります。
しかしながら、どうして「愛着トラウマ」は「過剰同調性」につながるのでしょうか。
先ほど、行き過ぎた「心の理論」の危険性をめぐる要点として、その「心の理論」が、純粋な他人への興味から育まれたのか、それとも強いられて発達させざるを得なかったのかが問題だ、と書きました。
「愛着トラウマ」の結果、異常発達する「心の理論」は、まさしく後者の強いられて発達させざるを得なかったものです。
「愛着トラウマ」の原因は何だったか、思い出してみてください。幼いころに、養育環境が混乱していて、他の人を信頼することを学べなかったことが、事の発端でした。
だれも心から信頼できず、養育者にさえ警戒してしまうとき、子どもはどんな戦略をとるでしょうか。敵か味方かもわからない見知らぬ人たちに囲まれているとき、あなたはどうやって生き延びますか。
きっと、顔色をうかがい、はたして相手が敵か味方かを知るために、過剰に空気を読んで先を予測しようとするでしょう。
「愛着トラウマ」を抱え持つ人は、本人は自分では気づいていないかもしれませんが、無意識のうちにそのような生き方をするようになります。
基本的信頼感が欠如しているために、常に周りの顔色や感情の変化にアンテナを張り巡らす生き方を、幼児のころからずっと続けてきたので、それが当たり前だと思っているのです。
「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() の中でも、大饗広之先生が、そのような強いられた空気を読みすぎる生き方について説明しています。
の中でも、大饗広之先生が、そのような強いられた空気を読みすぎる生き方について説明しています。
「小さな集団」にはそれぞれ、それなりの準拠枠というのがあって、いつも彼らはアンテナを立てて空気を読んでいなければならない。
みせかけの優しさを維持するにも緊張を緩めることができない。(p159)
常に相手の顔色をうかがっていて、その場その場で最善の身の処し方を無意識のうちに決定します。
そのため、普通の人以上に、場面ごとに空気を読んで別の自分を演じることが多くなります。
さきほど、心の理論の優れた人たちが活躍する職業の中に、小説家やシナリオライターのほかに、俳優が含まれていたのを覚えているでしょうか。
そのことが書かれていた哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)の文脈には、次のような記述がありました。
キラキラのマントを羽織り、髪を振り乱した妖精の正体は、空想の世界に浸っている三歳の女の子であってもいいし、『真夏の夜の夢』のタイターニアを演じる俳優であってもいいわけです。(p92)
「心の理論」の優れた、空想の友だちを持つ子どもが、IFの妖精になりきるように、「心の理論」の優れた俳優は、タイターニアになりきります。
そして、生存戦略として「心の理論」を異常発達させてきた愛着トラウマを抱える人たちは、ファンタジーの中でも、劇場の舞台の上でもなく、この日常世界のただなかで、空気を読んで、様々な自分を演じ分けることで、身を守るようになるのです。
それはまた、解離性障害の患者の特徴でもあります。
解離の構造―私の変容と“むすび”の治療論にはこう書かれています。
彼らはこのようなありありとした表象の中へと容易に没入する傾向がある。
読書でも映画でもテレビでも、その物語の中へ容易に入り込んで、その中の自分に成りきってしまう。(p203)
以前の記事で取り上げたとおり、解離性障害の人が、小説や詩、絵画、そして演劇などの芸術的な才能に秀でていることはよく知られています。それらは人並み優れた「心の理論」と感受性によって成り立っています。
![解離性障害と芸術的創造性ー空想世界の絵・幻想的な詩・感性豊かな小説を生み出すもの | いつも空が見えるから]()
さらに、この「心の理論」、つまり空気を読む、という能力は、あたかも鎖輪のようにして、子どものイマジナリーフレンドと、青年期のイマジナリーフレンド、そしてさらには解離性同一性障害(DID)を結び合わせています。
イマジナリーフレンドを持つ子どもは、空気を読む感受性が強いので、「いない人」のことまで考えてしまいます。
「心の理論」がもっと強くなると、それは過剰同調性へと発展します。その人たちは、空気を読み過ぎるあまり、場面ごとに違う自分、学校や家庭、友だちの前など、それぞれの場に最適な自分を無意識のうちに演じ分けるようになります。それこそが記憶はつながっていても、性格は異なるイマジナリーフレンドの源です。
さらに過剰同調性が強くなると、場面ごとに出ていた自分が独立し、自律性を持つ他人として分裂します。その場その場で最適な交代人格が日常をこなすようになり、記憶のつながりが失われます。
解離性同一性障害の人格交代とは、すなわち、究極の空気を読み過ぎる傾向なのです。
その証拠に、解離性同一性障害の専門家たちは、DIDの交代人格が無秩序に現れるのではなく、空気を読んで現れることを述べています。
たとえば続解離性障害![]() の中で岡野憲一郎先生はこう述べています。
の中で岡野憲一郎先生はこう述べています。
私がかつて担当したある患者は、診察室を一歩出た際に、それまでの幼児人格から主人格に戻ったことがあった。
…一般に解離性障害の患者は、自分の障害を理解して受容してもらえる人にはさまざまな人格を見せる一方で、それ以外の場面では瞬時にそれらの人格を消してしまうという様子はしばしば観察され、それが上記のような誤解を生むものと考えられる。(p151)
これはもちろん、DIDの人が演技をしているというわけではありません。むしろその逆で、無意識のうちに場の空気を読む傾向があまりに強くなってしまったために、自分で自分をコントロールできなくなってしまっているのです。
健康な人が、意識的に空気を読んで場に自分をあわせるよう苦労するのに対し、青年期のイマジナリーフレンドを持つ人は、過剰同調性のせいで無意識のうちに空気を読んで態度が変わってしまいます。それでもギリギリコントロールは保ってはいますが、もし、そのコントロールが失われたなら、そのときにはDIDに発展すると考えられます。
このように、愛着トラウマによって生じる過剰同調性は、イマジナリーフレンドと解離性同一性障害をつなぐミッシングリンク的な役割を果たしているので、岡野憲一郎先生が解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中で、解離性障害の人の診察で次のような点を重視していると述べているのも不思議ではありません。
の中で、解離性障害の人の診察で次のような点を重視していると述べているのも不思議ではありません。
成育歴の聴取の際には、その他のトラウマやストレスに関係した事柄、たとえば家庭内の葛藤や別離、厳しいしつけ、転居、学校でのいじめ、疾病や外傷の体験等も重要となる。
またその当時からICが存在した可能性についても聞いておきたい。また患者が幼少時より他人の感情を読み取り、ないしは顔色をうかがう傾向が強かったか、柴山(2010)の言う「過剰同調性」の有無がなかったかには注意を払う。(p100)
記憶にあるかどうかにかかわらず、幼いころのストレスフルな経験によって、「愛着トラウマ」を抱え持っているかどうか、そして、イマジナリーフレンドや、顔色を読み取る過剰同調性があったかどうかが、解離性障害の可能性を疑うリスク因子となる、ということなのです。
普通のIFと愛着障害のIFの違い
こうして、子どものイマジナリーフレンドと、青年期のイマジナリーフレンド、そして解離性同一性障害との関連性が見えてきたところで、それぞれの性質の違いがなぜ生じるか、という点をもう少し考えてみましょう。
まず、おさなごころを科学する: 進化する幼児観によると、健康な子どものイマジナリーフレンドと、解離性障害の子どものイマジナリーフレンドを比較したテイラー博士の研究では、次のようなことがわかったといいます。
空想の友達を持つことはこれらの精神疾患と関係しているのでしょうか。この点については、答えは否と言えそうです。
定型発達の子どもと解離性障害を持った子どもの空想の友達を比較した研究によると、前者は、空想の友達が実在しているとは思っていないのに対し、後者は空想の友達が実在していると信じているということです。(p241)
この場合、健康な子どもも、解離性障害の子どもも、イマジナリーフレンドを持っていましたが、その性質が少し異なっていました。
健康な子どもはイマジナリーフレンドが実在しないことを知っていたのに対し、解離性障害の子どもは実在を信じていたといいます。
これは、解離性障害の子どもが、現実と空想を混同してしまうことを示しているのでしょうか。
そうではないと思います。
基本的に解離性障害の人は統合失調症と違って、現実と空想の区別はついています。
空想の友だちが実在していると信じていた、というのは、統合失調症のように、妄想的な意味で信じている、という意味ではない可能性があります。
それを示唆しているのが、解離性障害の子どもが持つイマジナリーフレンドについて書かれた別の文献、こころのりんしょうa・la・carte 第28巻2号〈特集〉解離性障害![]() の子ども虐待の研究者、白川美也子先生の説明です。
の子ども虐待の研究者、白川美也子先生の説明です。
想像上の友人現象(imaginary companionship)は、正常児の20%から60%にみられるが、解離性障害の子どもには42-84%と多い。
正常児のもつ想像上の友人は、2歳から4歳までに現れ、通常8歳くらいまでに消失する。
養護施設の子どもたちの想像上の友人は(1)支援者、(2)パワフルな保護者、(3)家族成因などの役割をもっていることがあり、さらに被虐待の子どものそれは、「神」、「悪魔」などの名前をもっていることがある。(p97)
ここでは、まずイマジナリーフレンドは、健康な子どもよりも解離性障害の子どものほうに頻繁に見られることがわかります。やはり、「心の理論」が強まるにつれて、IFの頻度も上がるのでしょう。
そして、重要な点として、施設の子ども、つまり、強い愛着トラウマを抱えているような子どもたちのIFは、健康な子どものIFとは異なる特徴を持っているということがわかります。
健康な子どものIFは、「想像上の遊び友達」の名のとおり、気軽な遊び相手にすぎませんが、施設の子どものIFは、支援者、保護者、家族などの役割をもっていて、さらにトラウマが強いと、神や悪魔という名前さえ持っていると言われています。
イマジナリーフレンドの役割が異なると、当然、子どもにとっての重要性も変わるでしょう。単なる遊び相手であれば空想の産物で構いませんが、保護者や家族、神にまでなると、強い心の拠り所となっているはずです。
実のところ、健康な人でさえ、信仰心のある人は、神や仏の実在を信じているのではないでしょうか。しかしだからといってその人が妄想的なわけではありません。
つまり、解離性障害の子どもたちが、イマジナリーフレンドの実在性を信じていたという研究結果は、その子たちにとって、IFが、保護者や家族のような大切な存在だった、という意味ではないでしょうか。
なぜ「安全基地」としてのIFが必要なのか
このような、単なる遊び相手の域を越えた、保護者や家族のような役割を持つイマジナリーフレンドについては、前回の4つの考察の際にも詳しく扱ったのを覚えておられる方もいるかもしれません。
そこでは、愛着障害と関わる青年期のイマジナリーフレンドは、助け手や伴侶、さらには友人や恋人のような存在になる場合があることを説明しました。
そして、それら特別なIFは、愛着理論における、「安全基地」という役割を果たしているのではないか、という考察を含めました。
「安全基地」は、本来ならば母親などの養育者がその役割を果たします。「安全基地」という名のとおり、いつも無条件の愛で包み込んでくれる温かな存在がいるおかげで、さまざまな困難に立ち向かう勇気を持つことができ、疲れたときには帰ってきて身を休めることもできるのです。
しかし、さきほど取り上げた「基本的信頼感」が育っていない場合、すなわち「愛着トラウマ」を抱えてしまっている場合は、養育者は安全基地になりそこねてしまったので、だれかがその役割を肩代わりする必要があります。
「基本的信頼感」がないため、現実の人間にその役割を託すことができない場合、イマジナリーフレンドが保護者や、家族、神としてその役目を果たすのでしょう。
しかし、IFが安全基地としての役割を果たさなければならないのは、単に心理的な問題ではなく、実はもっと生物学的な意味があると思われます。
そのことを知るために、解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() から、愛着が果たす、生物学的な役割について調べてみましょう。
から、愛着が果たす、生物学的な役割について調べてみましょう。
この愛着トラウマは、具体的な生理学的機序を有している。
母親に感情の調節をしてもらえないことで交感神経系が興奮した状態が引き起こされる。
…しかしそれに対する二次的な反応として、今度は副交感神経の興奮が起きる。(p16)
まずここでは、愛着トラウマは、母親による感情の調節や、交感神経・副交感神経の働きと関係する、とされています。
そもそも愛着とは、生物学的に言えば、安心できる居場所を見分けるためのシステムです。
赤ちゃんは無力で無防備ですから、何よりもまず、どこにいれば、安心して眠っても構わないのか、ということを、 生まれてすぐに学習する必要があります。
生後半年から1年半ごろの早い期間に、自分のために特別な配慮を払ってくれた人、多くの場合、それは母親ですが、その母親の腕の中であれば、交感神経の警戒を解いて、副交感神経を働かせ、安心して眠ってよいのだ、ということを学びます。
そのように、交感神経を働かせ目覚めているべき場所と、副交感神経を働かせ、眠っても構わない安全な場所を見分けるシステムが、愛着と呼ばれる絆の正体なのです。
しかし、その絆が育まれず、愛着トラウマが生じると、何が起こるのでしょうか。
まず安心できる居場所がないため、警戒反応が強くなり、交感神経が過剰に興奮します。そして助けを求めて泣き叫ぶこともあります。
それでも保護が得られないと、何とか体を休めるために、母親に抱かれているわけでもないのに、副交感神経も強く働き始めます。
すると、本来はっきりとメリハリがついて、活動時と休息時に別々に働くはずの交感神経と副交感神経が、同時に興奮するという奇妙な状態になります。続く説明を見ると、その状態の異常さがわかります。
ちょうど「アクセルとブレーキを両方踏んでいるような状態」と考えると分かりやすいかもしれない。
そしてそれは、エネルギーを消費する交感神経系と、それを節約しようとする副交感神経系の両方がパラドキシカルに賦活されている状態であるとする。これが解離状態であるというのだ。(p17)
それは、「アクセルとブレーキを両方踏んでいるような状態」なのです。
この異常な状態は、混乱した無秩序な愛着パターン、通称「D型アタッチメント」と呼ばれて、以前の記事で詳しく取り上げました。
![人への恐怖と過敏な気遣い,ありとあらゆる不定愁訴に呪われた「無秩序型愛着」を抱えた人たち | いつも空が見えるから]()
基本的信頼感が育まれていないため、親や他の人と接する際、頼って心を休めたいと感じる反応と、傷つけられることを警戒して身構える反応とが同時に起こります。
もう少し成長すると、それは、他の人に一見親しげに振るまって接近しつつも、同時に警戒を緩めることができないという苦痛に満ちた人間関係に発展しがちです。
それこそが、かの「過剰同調性」です。他の人の顔色を読む強い「心の理論」を発達させ、優しく気配りしますが、心の底では、相手を信頼することができず、常に緊張しています。
本来なら同居するはずのない、人に対して親しげに振る舞う自分と、人に対して警戒する自分が同時に現れることが日常的に続くなら、行き着く先は一つ、自分が分裂した状態、すなわち「解離」なのです。
もちろん、解離の程度は人それぞれですが、解離は愛着トラウマによる「アクセルとブレーキを両方踏んでいるような状態」の結果と解釈すると、さらにわかることがあります。
たとえば、愛着トラウマを抱える人や、解離性障害の人は、感情の不安定さを抱えることが多いと言われています。
る子を愛せない母 母を拒否する子によると、子どもの愛着障害は、ADHDや双極性障害とよく似ていて、区別するのが難しいようです。子どもの愛着障害は、一般的に午前中うつっぽく、夜にハイテンションになりやすいそうです。
愛着障害に詳しい杉山登志郎先生は、子どものPTSD 診断と治療![]() の中でこう書いています。
の中でこう書いています。
この親の側に認められる気分障害を診断カテゴリーに当てはめれば、双極II型がほとんどである。
ところが、うつ状態と診断され、抗うつ薬のみが処方されていて逆に悪化したという例が多い。(p200)
その背後には愛着形成の障害があり、それゆえに情緒調整の障害が生じるのである。
…愛着障害を基盤にした気分調整不全が、成人に至ったときに双極II型類似の気分変動を生じるのである。(p201)
ここでは、子どものころに愛着トラウマを抱えた成人(親)は、双極性障害II型に似た気分変動を示しやすく、うつ病と誤診されていることも多いと言われています。
ここから思い出されるのは、先ほど引用した天才の脳科学―創造性はいかに創られるか![]() の、作家たちの健康状態について調査したデータです。作家たちが抱えていた病の多くは、うつ病または双極性障害でした。
の、作家たちの健康状態について調査したデータです。作家たちが抱えていた病の多くは、うつ病または双極性障害でした。
優れた「心の理論」の感受性を活かして、小説家として活躍する人たちと、愛着トラウマのために気分変動を生じた人たちが、同じ症状を示すのは決して偶然ではありません。
以下の記事で取り上げたとおり、愛着障害 子ども時代を引きずる人々 (光文社新書)という本によると、小説家として成功する人の中には、愛着トラウマを基盤とした空気を読み過ぎる能力を、創作という形で昇華している人が多いのです。
![文学や芸術を創造する「愛着障害 子ども時代を引きずる人々」 | いつも空が見えるから]()
解離性障害の専門家の柴山雅俊先生も、解離性障害―「うしろに誰かいる」の精神病理 (ちくま新書)![]() の中で、解離性障害はうつ状態や強い疲労感を伴い、双極性障害II型によく似ていると述べています。(p147)
の中で、解離性障害はうつ状態や強い疲労感を伴い、双極性障害II型によく似ていると述べています。(p147)
さらに、もう少し掘り下げてみると、先ほどの杉山登志郎先生は愛着トラウマが気分障害を生じさせる理由を次のように説明しています。
愛着行動とは幼児が不安に駆られたときに養育者の存在によってその不安をなだめる行動である。
やかて養育者の存在は幼児の中に内在化され、養育者が目の前にいなくとも、不安をなだめることが可能になる。
これこそが愛着形成の過程であり、その未形成とは、自ら不安をなだめることを不可能にする。(p201)
愛着トラウマとはすなわち、心の中に存在するはずの安全で包み込んでくれる親のイメージが存在していない状態、言い換えると、正常な安全基地の不在です。
安全基地が心の中に存在しなければ、不安が生じたとき、それを抑えこむことが難しいので、慢性的なうつ状態になりやすくなり、感情のコントロールも難しくなります。
そうした状況に置かれたとき、一部の子どもたちは、だれに頼るでもなく、自分自身でその問題を解決する適応反応を見せます。
自分の気分を調節してくれる養育者を現実に見いだせなかったのであれば、どうやって感情を調節すればよいのか。
答えは簡単です。現実にいないのであれば、自分で創り出せばよいのです。
それこそが、解離性障害の子どもや、施設で過ごす愛着障害の子どもに高率に認められる、保護者、家族などの役割を持ったイマジナリーフレンドの正体なのです。
IFはトラウマ記憶を再固定化する
こうして、自分で自分を守るための適応反応として生み出された「安全基地」としてのイマジナリーフレンドは、愛着トラウマを癒やす働きさえ持っています。
そもそも、トラウマが癒されるというのはどういうことなのでしょうか。
近年では、トラウマが癒される過程は「記憶の再固定化」、専門的には、治療的再固定化のプロセス(TRP)と呼ばれています。
TRPとは、簡単に言えば、エラーを起こしているファイルを開いて、中身を書き換えて、再保存するようなものです。
苦しいトラウマ記憶を思い出し、その記憶に別の解釈が加えることで、トラウマ記憶の修正を図ります。多くのトラウマ治療法は、たいていこのプロセスを含んでいます。
しかし、記憶の再固定化は、医師やカウンセラーでないとできない特殊なものではなく、日常的に生じています。
岡野憲一郎先生は、解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中でこう説明しています。
の中でこう説明しています。
まず記憶の再固定化ということについて強調しておきたいことがある。それは記憶が改編されるプロセスは、前章で紹介したTRPのようなある特殊な治療状況以外でも、常に起きている可能性があるということだ。
記憶の改編自体は日常生活でも起きていて、私たちはその原理を知らないうちに応用しながら、辛い体験を乗り切っている可能性があるのである。(p50)
記憶の再固定化によるトラウマ治療は、わたしたちの日常生活の中でも常に起きているとされています。たとえばどんな場合でしょうか。
ある苦痛な体験を持った後、私たちの多くはそれを誰かに話したくなるものだ。
胸の内を誰かに聞いてもらい、すっきりしたいと思うのは、おそにく過去にも似た体験があり、人に話すことで苦しみがある程度は楽になるということが学習されているからであろう。
もちろんだからといってその体験の後すぐに適切な話し相手が見つかるわけではない。
時にはその話し相手は、唯一の信頼できる友人でなくてはならないであろうし、別の場合には、客観的な立場にあり秘密を守ってくれるようなカウンセラーでなくてはならない。(p50-51)
岡野憲一郎先生が注目したのは、「会話」による記憶の再固定化です。
そもそもカウンセラーとの心理療法自体が会話ですが、ときに家族や親友が、有能なカウンセラー以上に助けになることは、多くの人が身を持って体験しています。
なぜそうした信頼できる人との会話が、記憶の再固定化を促し、トラウマを癒やすのか、ということについては、さらにこう説明されています。
トラウマ的な体験を持った後、私たちはしばしば奇妙な心の状態を体験する。それはそれを恐怖とともに体験した自分の方が異常であり、自分がされたことは必然であったという心境である。
あるいはこれを恐ろしいと感じているのは自分ひとりであり、その意味で自分は孤独である、という心境になることもある。
そんなときに一人で壁に向かってその体験を語ったところで、そこに記憶の改編が起きるはずがない。
ところが目の前に、自分を理解してくれる人が存在し、自分の感情に保証を与えてくれたり、それに共感してくれたりするという体験が生じると、たとえその人が気休めの言葉しかかけてくれないとしても、それもまた記憶の改編を生むのだ。(p52)
トラウマ的な経験をすると、さまざまな困惑や葛藤が沸き起こります。
そんなときに、一人で壁に向かってしゃべるのではなく、信頼できる人が話し相手になってくれるなら、新鮮な体験が生まれます。
自分が思い悩んでいることについて、まったく別の解釈を示してもらってハッとするかもしれません。あるいは、ただ聞いて共感してくれるだけでも、 自分は一人ではなく、ここにいても構わないのだ、という気づきにつながるかもしれません。
そうすると、トラウマ記憶は改編され、徐々にトラウマでない記憶へと修正されていくのです。
そして、もうお気づきと思いますが、このような信頼できる友人との対話は、愛着トラウマを持つ人がイマジナリーフレンドとの対話において経験していることそのものです。
傍から見ると、それは壁に向かってひとりごとを言っているように思えるかもしれません。もしイマジナリーフレンドが自分自身の空想の延長にすぎないとしたら、確かにそのとおりでしょう。
しかしイマジナリーフレンドは、ほとんどの場合、本人とは区別できる別人格として存在していて、会話によって違う観点から意見をやりとりしたり、本物の他人のように気遣いあったりすることができます。
逆説的に言えば、愛着トラウマを抱える人は、自分の空想の中だけで問題を解決することはできないのです。だからこそ、自分の一部を解離させ、自分とは別の人格としてのイマジナリーフレンドを生み出すのです。
前回の4つの考察で取り上げたとおり、 稀で特異な精神症候群ないし状態像の中でこう書かれていたのは、何の不思議もありません。
I.C.はその扱い方によってはこれを治療の協力者となすことも可能だと考えられるのである。(p49)
愛着トラウマにおけるIFは、治療の協力者となすことができるどころか、ある意味で治療者そのもの、専属のカウンセラーなのです。
もちろんそれは、自分自身で意図的に創りだしたものではなく、人の心にはるか昔から組み込まれている無意識の防衛規制という救済システムが、そうさせるのです。
人間にこのような防衛システムが組み込まれていることは、冒頭で触れた別の例「サードマン現象」にも如実に示されています。
以前の記事で取り上げたとおり、イマジナリーフレンドもサードマンも、人が危機に直面したときに、空想の他者を創りだすことで、脳を保護する働きであると考えられています。
![脳は絶望的状況で空想の他者を創り出す―サードマン,イマジナリーフレンド,愛する故人との対話 | いつも空が見えるから]()
この点については、日本における子どものイマジナリーフレンドの研究者である森口先生も、おさなごころを科学する: 進化する幼児観の中でこう同意しています。
各発達時期で支配的な行動が見られるものの、空想の友達がたとえば大人でサードマン現象として見られるように、時として他の発達時期で顔を出すことがあるのです。
つまり、加齢によってこれらの行動は消えるわけではなく、出てくる確率が相対的に低減するだけなのです。(p170)
社交的な幼い子どもが孤独を感じたときに子どもを支え守るために現れるのがイマジナリーフレンドであれば、大人が遭難などの極限状況で孤独に押しつぶされそうになったときに現れるのがサードマンです。
そして、青年期に、愛着トラウマによる「基本的信頼感」の欠如によって、この大勢の人がひしめきあう社会で遭難し、だれをも心から信頼できず、だれをも頼ることができないときに現れるのが、「安全基地」としてのイマジナリーフレンドだといえるでしょう。
脳の左半球と右半球の二つの自己のせめぎあい
IFがいかにして、愛着トラウマを抑えこむのか、という点をさらに調べてみると、興味深い事実が浮かび上がります。
解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() によると、愛着トラウマで生じる心身の問題をさらに生物学的に読み解くと、それは右脳の機能不全であると考えられています。
によると、愛着トラウマで生じる心身の問題をさらに生物学的に読み解くと、それは右脳の機能不全であると考えられています。
逆に愛着の失敗やトラウマ等で同調不全が生じた場合は、それが解離の病理にもつながっていく。
つまりトラウマや解離反応において生じているのは、一種の右脳の機能不全というわけである。
ショアがこれを強調するのには、それなりの根拠がある。
というのも人間の発達段階において、特に生後の最初の1年でまず機能を発揮し始めるのは右脳だからだ。(p19)
この点は別の記事でも詳しく取り上げましたが、愛着トラウマを抱える人は、左右の脳の連携が弱く、右半球の優位性が見られると言われています。
本来ならば論理的な思考をつかさどる左半球が、感情的な反応をつかさどる右半球を制御するはずですが、連携が弱いため、それがうまくいきません。
左半球によって右半球の感情的な反応が抑え込めないと、感情や記憶が、PTSDのフラッシュバックの形をとって暴走します。
しかし、ある人たちの場合は、左半球と右半球の連携が弱いとしても、別の方法で右半球の興奮を鎮める術を身につけます。
先ほどの説明の続きを見ると、次のような興味深いことが解説されています。
最後にショアが呈示する自己selfの理論が興味深いので、付け加えておきたい。
彼の説は、脳の発達とは自己の発達であり、それはもうひとつの自己(典型的な場合は母親のそれ)との交流により成立する、というものである。
そしてそこでも最初に発達を開始する右脳の機能が大きく関与している。
ショアは、自己の表象は左脳と右脳の両方に別々に存在するという考えが、専門家の間でコンセンサスを得つつあるという。
前者には言語的な自己表象が、後者には情緒的な自己表象が関係しているというわけだ。(p23)
人間の脳の左半球と右半球には、それぞれ別の自己が存在していると言われています。
これは荒唐無稽な話ではなく、以前の記事で紹介したとおり、てんかんの手術などでやむをえず脳の左右をつなぐ脳梁を切断した、分離脳(両断脳)の患者の研究によって確証されています。
脳の左右のつながりを失った患者は、あたかも二人の別々の自己が存在するかのように、右手と左手が、別々の意志をもって行動しました。
通常は、この二つの自己は統合されていて、多くの人は二人の自分がいるなどと思いません。しかし、愛着トラウマによって、左右の脳の連携が弱く発達してしまった人の場合、それぞれがある程度独立した人格を帯びています。
もちろん、愛着トラウマを抱える人の場合、脳の左右をつなぐ脳梁が切断されたわけではありませんから、完全に二つの自己にわかたれるわけではありません。
しかし脳梁の機能が弱く、普通の人よりも結びつきが弱いので、左半球を中心とした神経ネットワークの理性的な自己と、右半球を中心とした神経ネットワークの感情的な自己とを別々のものと感じやすいのかもしれません。
連携の弱い左半球は、その連携の弱さのために、あたかも別の人格であるかのように振る舞うことができ、「安全基地」としてのIFや内的自己救済者(ISH)として、母親の代わりに支えを与える場合があるのです。 このISHについてはもう少し先で改めて考えます。
内省的で柔軟な思考
おそらく、「安全基地」としてのIFを持つ人は、DIDの人よりも、比較的左右の脳の連携がまだ保たれているのでしょう。
自分とIFを別人格として認識しつつも、同時に両方を認識し、会話などのやりとりをすることができます。
その結果、おそらくは、暴走する右半球の感情を抑えこむために、左半球の理知的な働きがIFによって強化され、普通以上に内省的で柔軟な思考が形成されるのではないかと思います。
私見ではありますが、青年期を過ぎてもIFを持つ人は、実際の年齢以上に思考力が成長していることが多いように思えます。
その点は、「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() の中で、大饗広之先生も書いていました。
の中で、大饗広之先生も書いていました。
たとえば、社会的に成功していた43歳の男性S氏は、大饗先生に、若いころからイマジナリーフレンドを持っていたことを告白しました。
それは若い頃から少しはあったんですけど、最近になってそれが以前よりはっきりしてきた。「おいおい」と自分に誰かが呼びかけてくる感じです。
…頭の中でものを考えるとき、討論会やっている感じになるんです。それで自分は二重人格じゃないかと疑ったこともあった。
…論理的で慎重なことを言ってくるのは今の私に近い人……そいつはいたって平和主義で少し道を外れそうな自分を抑えてくれる。声も私と同じで「他の人」という感じはしないけど、思考は完全に第三者ですね。(p76)
S氏は、完全に第三者的な思考を持つイマジナリーフレンドと頭の中で会話を交わすことができました。イマジナリーフレンドの中には、論理的で慎重な、いわゆる脳の左半球の機能に特化した人格も含まれていました。
大饗先生は、そのようなS氏や、別のイマジナリーフレンドを持つ他の大人たちについて、こう評しています。
彼は内省力豊かでしかも柔軟な思考の持ち主であり、かなり苦痛と思われる体験も含めて冷静に回想することができた。(p77)
彼らはふつう以上に思考の柔軟性や内省能力を持っている人たちであった。(p86)
青年期以降もIFを持っていた人たちは、内省力豊で、ふつう以上に思考の柔軟性を持っていことが多かったのです。
おそらくは、一種の反転現象が生じているのでしょう。つまり、「愛着トラウマ」のせいで右半球の感情が暴走しやすく、それを抑えこむために左半球による理知的なIFを生み出し、常にせめぎあいを続けてきた結果、普通の人以上に思考力が発達していくのだと思われます。
優れた心の理論によって別人格を創造できるので、自分の気持ちだけでなく人の気持ちもわかるようになり、多角的・多面的な考え方ができるという事情も関係しているのでしょう。
こうした代償的な反転現象は、様々なケースで見られます。たとえば、先日亡くなった横綱千代の富士は、肩に慢性的な脱臼癖を抱えていましたが、それを克服するために人並み外れた筋力トレーニングをするようになり、横綱にまで上り詰めました。
明らかな弱点があると、それを克服するために正反対の域にまで成長していく、ということが、一部の人の場合に生じるようです。
解離性障害の人の場合もある程度同じことが言えそうです。解離性障害の人は、人が怖いという気持ちを抱えながら、繊細で優しい気配りが得意です。内省的で柔軟な思考の持ち主も少なくありません。
このような気配りは、すでに考えた過剰同調性の一面ですが、過剰同調性を示すには並外れた感情のコントロール脳力が必要なのも確かです。人前では、自分の感情や意欲を抑え、相手に合わせることになるからです。
そのようなコントロール能力は、ある程度、慢性的な感情の不安定さを抑えこむために発達したものなのでしょう。
そのようなせめぎあいが、限界を超えると、交代人格の解離にまで至ってしまいますが、ギリギリのところでバランスが取れていれば、IFとして認識されるのではないかと思います。
なんとかバランスがとれていれば、IFは絶望をわかちあう「安全基地」として、あたかも見守る親のように機能します。しかし、耐えられないほどのストレスがかかると、主人格が意識を失い、別人格が身代わりになって表に出てきて、あたかも子どもの代わりにやってあげる親のように、人格交代を伴うDIDに発展してくとみなせるかもしれません。
もちろん、青年期以降もIFを持っている人が、すべて内省力豊かで柔軟な思考を持っているとは限りません。
大饗先生も、反証となる一例を挙げていてイマジナリーフレンドを持ちながら、「内省的とはいえない」K氏の例を紹介しています。(p125)
しかし、K氏は、さきほどのS氏とは異なり、物心ついたときから周囲との疎外感を自覚していて、周囲に過剰に気を使うどころか、友人もおらず、ゲームに没頭して妻のことさえ気にかけない男性だったといいます。
大饗先生は、こうした点から、「彼が自閉的な傾向をもっていたという可能性が排除できない」と述べていて、別の要素の関与を指摘しています。この点については、後ほどセクション4で扱います。
過去の自分がIFになることもある
さて、ここまでのところ、脳の左半球を源として生じると思われる「安全基地」としてのIFについて考えてきました。
しかし、IFを持つ人たちは、右半球と左半球それぞれの1つずつのたった2つの人格しか認識していないとは限りません。DIDにしても、ISHのような理性的自己のほかに、たくさんの人格が出現するのです。
これらの多くの断片的な人格は、いったいどこからやってくるのでしょうか。
大饗先生は、過去の別モードの自分がIFとなるケースがあるという、興味深い説明を展開しています。
ある時期に急激なモード変換(物語の屈曲)が生じると、屈曲前のモードは単に忘却(抑圧)されるのではなく、まったく別の系列(アイデンティティー)として併存することになる。(p104)
人生の屈曲、すなわちクサビが打ち込まれる五歳までの天真爛漫だったナオミの記憶体系は、無意識へ垂直に抑え込まれずに、主体に並列する形で浮かび上がってきたのである。
五歳のときに断裂した部分が、彼女の歴史の全体性を外れて、別の人格体系(アキナ)として蘇ってきたのはなぜだろうか。(p104)
ここでは、IFの別人格アキナを持っていた、主人格のナオミという人について書かれています。
このケースでは5歳ごろに家庭内でショックとなる出来事があり、そのとき以降、周りの空気を読んで、性格や振る舞いを変えて生きていかなければならなくなりました。
すると、5歳まで育ってきた本来の天真爛漫な人格は封印され、5歳以降、必要に迫られて作った人格が、ナオミのアイデンティティになりました。
しかし5歳ごろまでの本来の人格は、消えてなくなったわけではなく、IF的な別人格、アキナとして、心の中に残り続けていたのです。
これは本来の人格がIFとなり、創られた人格が主人格となって生活してきた例といえるでしょう。
このような例は、珍しいものではないようで、大饗先生はこう説明しています。
解離された過去は「私」以外にだれか(多くはイマジナリーコンパニオンの形態をとる)に託されるようになる。「中心」そのものが多重化していくわけである(物語の多重化)。(p209)
IFを生み出すような人たちは、「過剰同調性」によって、その場その場に合わせてモード切り換えを続けながら生きてきているわけですが、過去のモードの名残が消えずに、IFとして独立することがあるのです。
これは、IFというよりは、幼いころにトラウマ経験を持つ解離性同一性障害(DID)の戦略として知られていて、「私」が、私でない人たち―「多重人格」専門医の診察室から![]() の著者ラルフ・アリソンはこうしたタイプをDIDではなく多重人格障害(MPD)として分けて考えています。
の著者ラルフ・アリソンはこうしたタイプをDIDではなく多重人格障害(MPD)として分けて考えています。
MPDの人は、新しい状況に対応するとき、その状況に即した新しい人格を創ることで対処していて、無制限に人格が増殖していきます。このMPDの軽いものが、モード切替ごとに生じて残っていくIFなのかもしれません。
このようにして、幼いころのモード切替の名残としてみられる別人格は、愛着障害とも関係しているのではないか、と岡野憲一郎先生は解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中で述べています。
の中で述べています。
ただし子どもの人格部分には、とても無邪気で創造的な振る舞いを示すものもある。一見明白なトラウマを抱えているわけではなく、ただ遊ぶことを目的に出てくるように見える子どもたちであるが、臨床上はこちらに出会うことのほうがむしろ多い。彼らの目的は何であろうか?
おそらくこちらはトラウマを背負った子どもの人格部分とは、多少なりとも異なる来歴を持つ可能性がある。
どちらかというと愛着障害に由来するのではないか。のびのびと甘え、遊ぶ体験を実際には持てず、ファンタジーの中でのみそれが実現していた場合、それもまた子どもの人格部分として隔離されている可能性があるのだ。
ただし最近用いられる「愛着トラウマ」の表現を用いるならば、こちらもまたある意味でトラウマ由来ということができるかもしれない。(p146)
ここで説明されているケースによると、愛着トラウマを抱える人の場合、ここまで考えてきた「安全基地」のような支え手となる別人格だけでなく、ただ無邪気に遊ぶことを目的とする子ども人格が存在する場合があるようです。
その子ども人格は、幼いころの天真爛漫で無邪気な自分、周りの空気を読んで、欲求や感情を抑制する前の本来の自分が、解離されて残っているものであるようです。
衝撃的なトラウマではなく、愛着トラウマから生じた過剰同調性のために空気を読んで、本来の子どもらしい自分を抑えた結果、そのときの満たされなかった自分が別人格となったりIFとなったりして、存在し続けることがあるのでしょう。
内的自己救済者(ISH)とは何か
このような考え方は、MPDを提唱しているラルフ・アリソンのもう一つの概念である内的自己救済者(ISH)とは何者か、ということに関して、いくらか洞察を与えてくれます。
アリソンは、多重人格の患者に見られる人格のうち、個々の役割に特化した交代人格が多くいる一方で、当人の過去すべてを知り、生まれたときから存在し、冷静で理知的かつ愛に満ち、他の人格を超越した特殊な人格がいることに気づき、内的自己救済者(ISH)と名づけました。
![多重人格治療のパイオニア ラルフ・アリソンの素顔―患者のために涙を流した医師 | いつも空が見えるから]()
アリソンは、だれでも理性的自己と感情的自己を持っており、DIDの場合は、理性的自己が独立しているように振る舞いはじめ、ISHとして認識されると述べています。
この理性的自己、またISHの特徴は、脳の左半球の特徴と非常に似通っています。感情的自己は右半球とみなせます。ISHがすべての人に最初から存在しているということからしても、おそらくは、脳の左半球にもともと存在する自己のことを指しているのでしょう。
おそらくは、DIDでは愛着トラウマのせいで脳の左右の結びつきが弱くなるために、左半球の自己が独立してISHとなるのでしょう。
そして、そのほかの多彩な人格は、その後の空気を読みすぎる生き方のモード切替の名残りとして創られていくものだと考えることができます。
アリソンの慧眼どおり、確かにISHと他の人格は別物であり、役割も異なるのだと思われます。
青年期のイマジナリーフレンドの場合も、やはりISHに近い「安全基地」としてのIFと、モード切替の名残としての多様なIFという二種類のタイプが存在している可能性があります。
しかしIFを持つ人は、DIDの人ほど左右の脳の結びつきが弱いわけではないでしょうから、「安全基地」としてのIFは、完全に左脳的で冷静沈着かつ論理的なISHと比べると、もう少し右脳的な感情要素も伴う、人間味のある人格として意識されるかもしれません。
子どものころの脳の名残
愛着トラウマから生じる一連のIFの考察の最後に、どうして愛着トラウマを抱える人は、本来子ども時代だけに生じるはずのIFを、青年期以降も持ち続けるのか、という点を考えておきたいと思います。
ここまで考えてきたことから明らかなとおり、幼い子どもの半数近くが経験するIFと、青年期以降に存在するIFは、別のものではありません。
どちらも、同様の脳の防衛機制によって創りだされる別人格であり、子どもの場合は孤独や退屈、青年期以降は愛着トラウマによる苦しさなどを和らげるために無意識的に生み出されます。
しかし、普通の人は、たとえ子ども時代にIFを持つとしても、その後の人生でトラウマなどの強いストレス経験をしたときに、IFが現れるということはまずありません。
ごくまれにサードマン現象のようにして、極限状況でIFが現れますが、一時的なものに過ぎませんし、何よりすべての遭難者がサードマン現象を経験するわけでもありません。
そもそも、IFを持つ子どもが20%-60%ほどの高率であるのに対し、IFを持つ大人は、冒頭で挙げた調査でも2.8%と、だいたい10分の1以下になります。
なぜ、たいていの人は大人になるとIFを持たなくなるのに、愛着トラウマを抱える人はIFを持ち続けることができるのでしょうか。
これはおそらく、愛着トラウマが脳の発達に影響を及ぼし、子ども時代の名残を残した脳のまま、大人になるという仕組みが絡んでいるようです。
たとえば、おさなごころを科学する: 進化する幼児観の中にはこんな説明があります。
子どもの頃、世界はもっと私たちに身近で、鮮明だったように思えます。太陽はまぶしく、草木の緑は濃く、水は本当に青い空をしていました。虫と会話をし、小人の足跡を見つけ、神様の存在を感じることができました。
…詩人などの一部の人間だけが、その感覚を大人になっても保持し、表現できるのかもしれません。(ii)
この場合、詩人になるような人は、おそらく子ども時代の感覚、つまり脳の性質を溜まったまま成長していったのでしょう。
子どものころは脳がまだ十分発達しておらず、抑制機能の基盤である前頭葉も未熟なので、感覚の統合が十分ではなく、空想の友だちや、共感覚、絶対音感などの不思議な現象が当たり前のように存在します。
しかし、赤ちゃんはすべて共感覚や絶対音感を持ち、幼児の半数近くがIFを持つのに、大人になると、それらはいずれもまれになります。脳が発達すると、各部分の結びつきが安定し、解離しにくくなるからです。
ところが、ADHDやアスペルガー症候群などの発達障害の人は、大人になっても共感覚を持っている場合があります。これは脳の発達の未熟さから、子ども時代の名残が残っているためです。
同様のことが、愛着トラウマの場合も生じます。近年の研究によると、愛着トラウマは、脳の発達を妨げ、生来の発達障害と似たような成長の遅れをもたらすことがわかっています。
それどころか、生来の発達障害よりも、子ども時代の過酷な環境のほうが脳の発達を妨げる度合が強いとも言われていて、「発達性トラウマ障害」(DTD)という概念が提唱されています。
![発達性トラウマ障害(DTD)の10の特徴―難治性で多重診断される発達障害,睡眠障害,慢性疲労,双極II型などの正体 | いつも空が見えるから]()
それで、愛着トラウマを抱えた人や、後ほど取り上げるアスペルガー症候群などの発達障害の人がIFを持ちやすいのは、脳の発達が定型的でなく、大人になっても解離しやすさが残っているからなのかもしれません。
子ども時代の脳の名残を抱えたまま大人になってしまうので、イマジナリーフレンドのような、本来は子ども限定の不思議な現象を感じ続けることができるのでしょう。
ここまで、愛着トラウマや心の理論というキーワードを通して、子どものイマジナリーフレンドと、青年期のイマジナリーフレンドの関わりについて考察してきました。
続くセクション3では、解離に焦点を当てて、青年期のイマジナリーフレンドと、解離性同一性障害(DID)の交代人格のつながりについて考えてみたいと思います。
第三章 解離的な「夢」として考えるIF
ここまで考えてきた子どものイマジナリーフレンドも、愛着トラウマに由来する青年期のイマジナリーフレンドも、 いずれも根底にあるのは防衛機制の解離というメカニズムの働きです。
解離には、わたしたちが日常的に経験している没頭体験や白昼夢などの程度の弱い解離から、空想の友だちを創り上げ、人格が別れてしまう程度の強い解離まで、様々なものが含まれます。
このセクション3では、そもそも「解離」とはいったい何なのか、という点を睡眠中の夢との関係で掘り下げ、イマジナリーフレンドとDIDの交代人格のつながりについて考察します。
IFとDIDは連続するもの
これまで、IFとDIDは関連性のある現象なのかどうか、という点について、多くの専門家が議論してきました。
おもな争点となっているのは、記憶の断絶があるかどうかです。
DIDでは、一般に、人格交代している間の記憶は失われることが多く、それぞれの人格の間で記憶が隔てられる健忘障壁が見られるとされています。
それに対して、IFはそれぞれの人格間の記憶は筒抜けであり、健忘障壁はありません。
では、IFとDIDはまったく別物なのかというと、そうではないようです。
問題なのは、専門家たちが理論先行で議論を戦わせてきた結果、現実に即していない机上の空論が組み立てられてしまったことです。
これまで、人格交代がありながら健忘障壁はほとんどない解離性障害は、DIDとみなすことはできず、DDNOS(特定不能の解離性障害)と診断されてきました。
ところが、岡野憲一郎先生が、解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中で述べているところによると、典型的なDIDなどというのは非常にまれで、ほとんどの症例がDDNOSになってしまう「ゴミ箱満杯問題」が生じていたそうです。(p116)
の中で述べているところによると、典型的なDIDなどというのは非常にまれで、ほとんどの症例がDDNOSになってしまう「ゴミ箱満杯問題」が生じていたそうです。(p116)
そこで近年、新しい診断基準であるDSM-5が作られた際、次のような変更が加えられたそうです。
ここではDDNOSに列挙されていたものを思い出そう。そこには「例」として、1.DIDの不全型(明確に区別されるパーソナリティ状態が存在しない。重要な個人的情報に関する健忘が生じていない)…などが挙げられていた。
このうち1.DIDの不全型については、上記のように診断基準が緩められたことで、以前はここに入り込んでいたケースの多くがDIDとして診断を下される可能性があろう。(p116-117)
つまり、DIDには健忘障壁が必須、という考え方は緩められ、これまでイマジナリーコンパニオンとみなされていたケースがDIDとみなされる可能性が出てきたということです。
この変更によって、診断名が変わるかもしれない有名な、ただし架空の人物に、ジキル博士とハイド氏がいます。
意外に思えるかもしれませんが、しばしば多重人格の代名詞とされているジキル博士とハイド氏と、これまでの診断基準だと、厳密にはDIDではなく、イマジナリーコンパニオンとみなされていました。
「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() の中で、大饗広之先生はこう述べています。
の中で、大饗広之先生はこう述べています。
主人格が別人格を認識している場合には、それは主人格による空想の産物として扱われ、DIDの交代人格とは似て非なるものとみなされ、イマジナリーコンパニオンという名称があてられる(ジキル博士にとってのハイド氏もそれにあたる)。
また解離した人格ーが人格としての深みを欠き、要素的感情(たとえば怒り、喜びなど)しか持たない場合などには人格断片という呼称があてられる。
しかし交代人格がICから発展する可能性も以前から指摘されており、両者の関係には依然として曖昧な点が多い。(p178)
なぜジキル博士とハイド氏が多重人格でないのか、というと、ジキル博士とハイド氏の間に。健忘障壁はなく、二つの人格はそれぞれの存在をよく知っていたからです。
しかし大饗先生が述べているとおり、たとえその時点では健忘障壁が存在しないとしても、やがてICからDIDに発展する可能性が、かねてより指摘されていました。
大饗広之先生は、臨床で出会うICの場合も、ハイド氏のように人格としての一貫性が認められ、単なる空想の産物とは言いがたいという点を述べてています。
実際に人格の多重化を訴えるケースを覗いてみると、主人格と交代人格をそれほど簡単には区別できないケースが圧倒的に多い。
そして交代人格(IC)にも人格としての一貫性が備わっていることが少なくないのである。(p179)
そして実際の臨床では、DIDとICの境界線を引くのが難しいケースも少なくないことを述べています。
ヨウコのような症例においてはICとDIDを質的にわけることができないのである。
両者には断片的な性格のものから人格として高度に統合されたものまでさまざまな段階のものがあり、少なくとも健忘の程度によって質的に区別することは難しい。(p181)
結局のところ、健忘障壁があれば病的なDID、互いに会話できればイマジナリーコンパニオンという分け方は、学者が作り出した机上の空論に過ぎず、臨床の場では、両者は複雑に絡み合っているのです。
もちろん、これは、IFを持つ人がみな、DIDのような状態に発展していくという意味では決してありません。
次のセクションでも改めて取り上げる点ですが、これは自閉スペクトラム症の連続性と似ています。
自閉スペクトラム症では、明確な境界線は存在しておらず、少し自閉的なもののほとんど気づかれない自閉症表現型(BAP)と呼ばれる人たち、ある程度自閉的なもののコミュニケーション能力を備えたアスペルガー症候群(AS)の人たち、そして、重いコミュニケーション障害を抱えるカナー型自閉症の人たちなどが連続的に分布しています。
しかし、だからといって自閉症表現型の人がアスペルガー症候群に発展したりするわけではありません。
同様に、人格の多重化も、一瞬だけ人格交代が生じる人、会話できるイマジナリーフレンドを持つ愛着トラウマを抱えた人、人格交代して健忘障壁を伴うDIDの人などが、連続性をもって分布しているようです。
しかしこの場合も、連続性があるとはいえ、イマジナリーフレンドがDIDに発展するかというと、必ずしもそうなるわけではありません。
そのようなわけで、人格の多重化スペクトラムという観点から見ると、DIDのような典型例は少なく、むしろ中間的な位置にあるイマジナリーフレンドが思いのほか広く存在している可能性があります。
また、これまで、DIDのような人格の多重化は、性的虐待などの衝撃的なトラウマをきっかけに発症するものと考えられていましたが、近年は見方が変わってきています。
岡野憲一郎先生は、解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中で、次のように述べています。
の中で、次のように述べています。
すなわち解離性障害とは、それが基本的にはいわゆる「愛着トラウマ」による障害のひとつと理解されることを常に念頭に置くべきなのである。(p15)
解離性障害、または解離性同一性障害(DID)は、ここまで考えてきたような愛着トラウマを発端とする症状のうち、極端なケースであると考えることができます。
実際に、解離性障害の臨床では、PTSDのような明確なトラウマ因が見つからないことも多いと言われています。
それに解離性障害には、PTSDなどについて考えるようなトラウマやストレスが必要条件として存在するべきなのかについての識者の見解は統一されているとは言えない。
私の臨床場面でも、過去の明確なトラウマ因を見いだせないケースは実際に体験されるのである。(p106)
もし原因がショッキングなトラウマではなく、乳幼児期の愛着形成の失敗にあるのだとしたら、トラウマ因が見当たらないケースがあるのも当然ですし、普通の家庭の子どもがたまたまやむを得ない事情で愛着形成に失敗したせいで、のちのち解離性障害になりやすくなるケースもあるでしょう。
人格の多重化の根底にあるのは、結局のところ、セクション2で見たような、乳幼児期の愛着トラウマによる左右脳半球のつながりの弱さなのです。その中でも特殊で程度の重い事例が、DIDと呼ばれる多重人格だと理解することができます。
解離は感覚遮断から始まる
それにしても、このような人格の多重化を引き起こす要因である、解離とは何なのでしょうか。なぜ多重化してしまうのでしょうか。
解離にはさまざまなメカニズムが関与していると思われますが、解離を引き起こす大きなきっかけは感覚遮断だと思われます。
感覚遮断とは、防衛反応として、外部からの刺激をシャットアウトする脳の働きのことです。
感覚遮断は、ごく普通の人にも生じることがあり、そのような場面ではだれもが解離性障害のような症状を一時的に経験します。
たとえば、臨死体験はその一つで、死の危機に瀕した際に、脳が危機を感じて感覚遮断することで、解離性障害に見られるような幻覚や体外離脱が生じます。
幻覚とはすなわち、外からの視覚や聴覚の入力がなくなったときに、脳が記憶の中から感覚を再生するものであり、体外離脱とは解離性障害の離人症のような体の感覚統合が失われている状態です。
そのあたりの詳しい内容については、以下の記事で詳しく説明しています。
![なぜ人は死の間際に「走馬灯」を見るのか―解離として考える臨死体験のメカニズム | いつも空が見えるから]()
さらに、感覚遮断は、危機的な状況に直面しなくても、実はわたしたちが毎日のように経験している日常的な現象です。
「夢」の認知心理学![]() という本には、レム睡眠の際に起こる生理的な現象について、次のように書かれています。
という本には、レム睡眠の際に起こる生理的な現象について、次のように書かれています。
内的に活性化した脳波、睡眠を維持し、夢を持続させるために外界からの刺激を遮断する。(p14)
レム睡眠とは、わたしたちが毎晩経験している浅い眠りのことですが、そのとき、脳は外部からの感覚を遮断しているのです。
覚醒とレム睡眠は電気的には似た状態であるが、前者が外部からの感覚と同期しているが、レム睡眠時には同期しない点で決定的に異なるのである。(p37)
この説明が示す通り、レム睡眠の最中には、覚醒時と同じように脳が活発に働いています。
覚醒時と異なっているのは、感覚が遮断されていることだけです。そうすると何が起こるのでしょうか。
実はレム睡眠とは、わたしたちが様々な夢を見ている状態です。夢はノンレム睡眠のときにも見ますが、一般によく言われる不思議な内容の夢は、レム睡眠の最中に見ているとされています。
そして、感覚遮断されているときに見る夢の内容は、解離性障害で生じるような幻覚や意識の変容と非常に類似しています。
また、感覚遮断されているレム睡眠の最中にたまたま目が覚めると、意識は目覚めているのに、体からの信号はプロックされているため、体が動かせない金縛りや幽体離脱を経験する場合があります。これらも解離性障害ではよく見られるものです。
それで、「解離」とは「感覚遮断」であり、解離性障害の人は、目が覚めているときに感覚遮断のメカニズムが部分的に働いているせいで、離人感や幻覚、浮遊感など、あたかも夢のなかのような現象が生じるのだ、と解釈することができます。
HSPー敏感すぎる人たち
しかし、いったいなぜ、解離性障害の人たちは、目覚めていながら、レム睡眠のときのような感覚遮断のメカニズムが働いてしまうのでしょうか。
その理由は、これまで考えてきた「愛着トラウマ」や強すぎる「心の理論」と結びついています。
愛着トラウマとはすなわち、「基本的信頼感」が欠如していて、安心できる居場所がなく、他の人を心の底から信頼できない状態でした。常に人の顔色をうかがって警戒している過敏状態にあるということです。
また、心の理論が強すぎるというのは、他の人に気持ちに敏感すぎて、感情移入しすぎる傾向のことでした。同時にちょっとした感情の行き違いや批判に過敏になっているともいえます。
このような心の敏感さを抱えていると、当然ながら、身の回りのものからくる感覚刺激は強すぎて、圧倒され、パニックになってしまうでしょう。
人混みに行くだけでも疲れ果てたり、ニュースを見るだけでもいちいち無意識のうちに感情移入してしまってくたくたになるかもしれません。
そうすると、自己防衛のために、解離、つまり感覚遮断のメカニズムが働き出すのは、ごく自然なことです。
また、感覚遮断が働くのは、愛着トラウマのような後天的な経験のせいだけではないかもしれません。
たとえばセクション4で取り上げる自閉スペクトラム症のアスペルガー症候群では、生まれつき五感のさまざまな感覚過敏を抱えていることが多く、トラウマ経験のあるなしに関わらず、外部からの刺激が強すぎて解離しやすいと言われています。
さらに、ひといちばい敏感な子![]() によると、近年では、遺伝的な傾向として、高度に過敏で感受性が強い人が5人に1人程度の割合で存在するとされていて、HSP( Highly Sensitive Person)と呼ばれています。
によると、近年では、遺伝的な傾向として、高度に過敏で感受性が強い人が5人に1人程度の割合で存在するとされていて、HSP( Highly Sensitive Person)と呼ばれています。
また、母という病 (ポプラ新書)![]() によると、愛着の安定性は完全に後天的なものではなく、遺伝要因が25%程度関係しているようです。
によると、愛着の安定性は完全に後天的なものではなく、遺伝要因が25%程度関係しているようです。
これは、おそらくADHDの関わるドーパミン関連の特定の遺伝子タイプなどを持っていることによる感受性の強さのため、他の子どもでは問題とはならない程度の養育環境でも不安定な愛着を生じやすいのではないかだと言われています。(p94)
このような生まれつきの遺伝的な過敏性が、HSPのような感受性の強さを生み、人よりも傷つきやすかったり、、愛着トラウマや感覚遮断を引き起こしやすい体質として関与している可能性があります。
ちなみに、感覚過敏への対処法が感覚遮断による解離である、というのは医療現場でも難病の治療に応用されています。
たとえば、全身に激痛が走る痛覚過敏の病気である線維筋痛症の治療として、アイソレーションタンク(感覚遮断タンク)を用いて痛みを軽減する治療法が試されています。
また「病は気から」を科学するによると、過敏性腸症候群(その名の通り腸の感覚過敏)の治療法として、催眠療法によって人為的に解離状態を作り出し、感覚遮断する方法が成果を挙げているそうです。
これらの例からわかるとおり、感覚遮断による解離というのは、病的なメカニズムどころか、健全な体の反応であり、世の中には解離がうまく働かないせいで痛みなどの過敏に悩んでいる人も少なくないのです。
統合失調症のような「疾患」ではない
ここで、少し話を戻しましょう。
先ほど、解離性障害とは、目覚めていながらにして、感覚遮断が生じ、あたかも夢の中のような不思議な感覚が生じている状態だと説明しました。
しかし、このような説明は、これまでしばしば統合失調症に適用されてきました。
統合失調症は奇妙な幻覚を伴い、判断能力も失われているので、あたかも起きながらにして夢を見ているような状態だと言うわけです。
しかしこれもまた、現場のデータを無視した研究者による机上の空論である可能性があります。
「夢」の認知心理学![]() では、レム睡眠の間に見る夢の内容を分析したところ、次のような意外な結果が得られたそうです。
では、レム睡眠の間に見る夢の内容を分析したところ、次のような意外な結果が得られたそうです。
大人と子どもの両者からレム期からの報告についての実験室研究の結果は、夢見は一般に考えられているほど奇怪なものとは程遠いことを示すものであった。(p73)
全体としてみると、実験室での研究と自宅での研究は、夢の内容の特徴が高度に感情的で奇怪で妄想あるいは統合失調症のような内容を持つという証拠はない事を示している。(p83-84)
なんと、レム睡眠の間に見ている夢は、多くの場合、統合失調症の世界のような奇怪なものではなかったのです。
夢はもっと日常的な内容が多いのに、わずかな奇怪な例が印象に残ることが多いために、誤った印象を抱かれていたのでした。
さらに、夢は奇怪なものであるという誤解だけでなく、統合失調症の性質のほうにも、とても大きな誤解が生じています。
解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() にはこう書かれていました。
にはこう書かれていました。
他方の幻視はどうか。統合失調症においては少ないとされる幻視は解離性障害では比較的多く聞かれる。
また統合失調症の幻視が奇怪な内容であるのに対し、解離性障害の幻視の内容はおおむね現実的で、過去のトラウマのフラッシュバックという色彩を持つ。(Bremner,2009)。(p125)
統合失調症では、幻視は少ないのです。
そして統合失調症では幻視が奇怪な内容であるのに対し、解離性障害では幻視が頻繁にみられ、内容はもっと日常的だとされています。
この説明から明らかなとおり、夢の内容とよく似ているのは、統合失調症ではなく、解離性障害です。
夢の主な要素は視覚イメージですが、統合失調症では視覚的な幻覚は少ないこともそれを裏づけています。
「夢」の認知心理学![]() には、夢の視覚的要素について、こう書かれていました。
には、夢の視覚的要素について、こう書かれていました。
夢の内容を作り出す能力は覚醒時のイメージ能力を反映している、すなわち夢≒覚醒時のイメージと言えそうです。
夢は覚醒時のイメージと似たようなことが感覚遮断状態で起こる現象であるということです。(p86)
解離性障害の人は、絵などの芸術的才能に優れた人が多いですが、視覚的イメージ力が通常よりも高いようです。
おさなごころを科学する: 進化する幼児観によると、イマジナリーフレンドを持つ大学院生を対象とした研究では、視覚イメージ力が高い傾向が得られたとも言われています。
麻生博士らの大学生を対象にした研究では、大学生でも、空想の友達の強い視覚的イメージを持つことが報告されていますし、筆者らの研究でも、空想の友達を持つ大学院生は、空想の友達を持たない大学院生よりも、視覚イメージを生成する能力が高いことが示されました。(p251)
感覚遮断による解離傾向が生じている人たちは、幻視を見るほどではなくても、空想癖や白昼夢の傾向があるために視覚イメージが発達しやすいのでしょう。
さらに感覚遮断と解離傾向が強くなると、起きながらにして少し夢を見ているような感じになり、本来は夢の中で生じるはずの視覚イメージが現実に重なって見える場合があるようです。
解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() にはこうあります。
にはこうあります。
また幻視は統合失調症ではあまり見られないものであるが、解離性の幻覚としてはしばしば報告される。
それがIC(空想上の友達)のものである場合、その姿は視覚像として体験される場合もそうでない場合もある。
またそれが実在するぬいぐるみや人形などの姿を借りるということもしばしば報告される。(p100)
おそらく本物の夢を見ているときほどに感覚入力が遮断されているわけではないものの、感覚入力がいくらか減っていて、そのぶんを幻視で補っているのかもしれません。
これと同様の状況には、視力が衰えた老人に生じるシャルル・ボネ症候群があります。こちらも、視覚からの入力が少なくなることで、現実に重なる幻が見えるようになります。
ただし、解離性障害では目の機能そのものが衰えたわけではなく、脳が外部からの入力を抑制するために、内部から幻が再生されるのです。
このように考えてくると、解離性障害とは何なのか、ということについて、極めて重要な洞察が得られます。
解離性障害で生じる状態は、夢のメカニズムと非常によく似ていますが、夢は、健康な人がだれでも毎晩のように見ているありふれた現象です。
解離性障害では昼間に感覚遮断が生じるために、起きながらにして夢を見ているような状態に近づきますが、そもそも感覚遮断は異常なことではなく、毎晩普通に生じるものです。
そうすると、解離性障害の人の脳では、何か異常な事態が生じているわけではなく、だれにでも備わっている防衛反応が、普通より強く働いているだけだ、ということになります。
解離性障害は、脳の「障害」あるいは「病気」ではなく、強いストレス環境に対して、脳が自分を守ろうと働いている状態ではないか、という見方ができます。
それはちょうどインフルエンザになったときと同じです。インフルエンザでは、ひどい不調が生じますが、それは体が壊れたせいではなく、ウイルスという外敵に対して免疫系が闘っているためです。機能は正常なので、危機が去れば元に戻ります。
解離性障害の場合も、どうやらそれと同じようなことが、脳の中で起こっているようです。
解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中で、岡野先生は、統合失調症と解離性障害の最も大きな違いについて、こう説明しています。
の中で、岡野先生は、統合失調症と解離性障害の最も大きな違いについて、こう説明しています。
端的に言えば、精神病の代表格ともいえる統合失調症は、一般的に時と共に人格の崩壊に向かい、予後も決してよくない。
他方、解離性障害は社会適応の余地を十分に残し、また年を重ねるにつれて症状が軽減する傾向にある。
両者が全く別物であるというのは、この予後の観点から特に言えることなのだ。(p123)
統合失調症は予後が悪く、どんどん悪化していくのに対し、解離性障害は年と共に回復していくのです。
このことからすると、統合失調症が明らかな脳のトラブルであるのに対し、解離性障害はウイルスに対して免疫系が戦うように、愛着トラウマに対して脳の正常な防衛機制が戦っている状態だとみなせます。
冒頭で、多くの子どもが持つ空想の友だちが、解離性同一性障害と地続きだと言っても、病的なものだとか、危険な要素を持っている、という意味ではなく、どちらかというとその逆だ、と書いたのを覚えておられるでしょうか。
それはつまり、イマジナリーフレンドやDIDのような人格の多重化現象は、本質的に言って害を及ぼす病気なのではなく、危機に面した心を守るために脳が働かせる正常な防衛反応なのだ、という意味なのです。
適応的な「夢」としてのIF
解離による人格の多重化が正常な防衛反応であることを示すさらなる根拠は、解離によって生じる別人格と、夜に見る夢とが、どちらも同じような役割を持っているようだ、ということです。
夢は何のために見るのか、という点は未だ多くの論争がありますが、「夢」の認知心理学![]() によると、以下のような適応的な役割があるという研究結果があります。
によると、以下のような適応的な役割があるという研究結果があります。
両方とも夢は適応的な機能に役立つということを主張できるものであった。
一つは、我々はストレスフルな出来事を統御できるようになるために夢見るということ。
もう一つは、心理学的にそれを補償するために現実のストレスとは反対方向の性質をもつ出来事を夢見るということである。(p102)
かねてから夢は記憶の定着の役割を持っているとされることがありましたが、近年ではレム睡眠を削っても記憶の定着が妨げられることはなく、エピソード記憶の定着はノンレム睡眠中に行われているのではないか、と言われているそうです。
その代わりにレム睡眠は手続き記憶の定着や感情の整理を担っており、その現れが夢なのかもしれないという意見があるそうです。
実際に夢の内容を調べると、ストレスに関わる感情の整理に役立っているらしきことがわかりました。
ただし、一般に考えられているような、ホラー映画を見れば怖い夢を見るといって関連の仕方ではなく、その反対、つまりストレスとなった出来事と正反対の性質の夢を見やすいことがわかったのです。
眠る前に受けた刺激に関しては夢に現れるのではないかと一般的に思われているかもしれないが実験の結果はむしろ逆になる傾向が多く確認されている。
フロイトは夢の内容は昼間の経験で抑圧した「日常の残渣」が現れるとしたが、どうやらこの説はあまり説得力を持たないようである。
しかし、強いストレスの場合には当てはまるケースもあるようであるが、あまりに強すぎると「抑圧」されてしまうらしい。(p109)
この説明が示す通り、基本的に、夢は受けたストレスと正反対の内容になることで、感情を調節する「補償」の役割を果たします。
しかし、ストレスが強すぎると、内容もストレスフルなものになる場合があります。
そして、ストレスがあまりに強すぎると、今度はそれが抑圧されて、そもそもその夢を見ないようです。
これはイマジナリーフレンドなどの人格の多重化における反応と極めてよく似ています。
人格の多重化は、ある程度の慢性的なストレスのもとでは、イマジナリーフレンドという形で現れ、ストレスとは正反対の励まし手として、愛着トラウマに対する安全基地として、補償的な役割を果たします。
しかしよりストレスが強くなると、バランスが崩壊して、悪意を持つ人格が現れる場合があります。
ストレスがあまりに強すぎると、DIDとなって記憶が分断され、トラウマ記憶を隔離する健忘障壁が生じます。
どうやら、夢と人格の多重化は、感覚遮断による解離という同じメカニズムによって支えられているため、果たす機能もよく似ているようです。
言ってみれば、イマジナリーフレンドとは、起きながらにして不思議な夢の世界の住人と出会っているようなものであり、DIDとは、起きながらにして悪夢に悩まされているようなものなのです。
IFを持たない「心が空っぽ」な人たちとの違い
イマジナリーフレンドや解離性障害は、心を守る適応的な働きだとすると、次のような疑問が生じます。
本当に問題なのは、防衛機制である解離が生じない場合ではないでしょうか。
セクション2では愛着トラウマについて考えましたが、愛着トラウマを抱える子どもすべてが保護者のようなIFに出会うわけではありません。
ある意味で、愛着トラウマを癒やすためにIFが現れるのは幸運なケースであり、「安全基地」をどこにも得られないまま、ひたすらさまよう、心が空っぽな人は決して少なくないのです。
「安全基地」としてのIFが創られるのは、解離という防衛機制の働きですが、解離が弱い人たちは、心を守るためにIFが作られることはありません。
重い愛着トラウマがあるのに、心を守る解離が十分に働かない場合に生じるもの、それは何でしょうか。
それは、トラウマ経験と最もよく結び付けられる病気、すなわち心的外傷後ストレス障害(PTSD)です。
PTSDは、脳科学的には解離と正反対の現象だと言われています。解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() ではこう説明されていました。
ではこう説明されていました。
ところで解離において右脳で起きていることを知るためには、心的外傷後ストレス障害(以下PTSDと記載する)の右脳で起きていることを理解する必要がある。
解離とPTSDは、ともに心的なトラウマに対する心ないしは脳の反応といえるが、そこではおおむね逆のことが起きているものとして説明し、理解するのが最近の傾向である。(p19)
PTSDと解離は、正反対の現象ではあるものの、連続性を持つ、人間の危機対処システムの一部です。
人間の危機対処システムは二段構えで構成されています。
獰猛なライオンに出くわしたときのことを考えてみてください。
まず、頭がパニックになって何も考えられなくなり、なんとかして闘うか、あるいはその場から逃れようとします。
これはストレス反応として有名な「闘争か逃走か」の反応です。
しかしそれがうまく行かず、ついにライオンに組み伏せられてしまったら、第二段階のシステムに移行します。
それは「固まり・麻痺」反応で、仮死状態になったり、気絶したりする状態です。
この二段構え危機対処システムは、突然の危機のときだけでなく、日常のストレスに対しても生じます。
一段階目の「闘争・逃走」反応がPTSD、ニ段階目の「固まり・麻痺」が解離に相当します。固まり・麻痺は、もはや逃げられない状況で、感覚遮断をして苦痛をやり過ごそうとする反応です。
すると、危機の際の反応は、
積極的なもの……闘争、逃避
消去的なもの……固まり、麻痺
の2種類に分かれることになる。そして後者の消極的なものは解離に関係づけられるというわけである。(p22)
セクション2で、愛着トラウマから解離に至る人たちは、まず交感神経(アクセル)が過剰興奮し、次いで副交感神経(ブレーキ)も過剰反応するという説明を引用しましたが、それらがすなわちPTSDと解離なのです。
問題は、解離という防衛機制が弱いせいで、第一段階の「闘争・逃走」のままで、第二段階の「固まり・麻痺」が起動しない人たちです。
交感神経が過剰反応してパニックになるだけで、それを抑えこもうとして副交感神経が働くことがありません。
すると、愛着トラウマのときに説明したような、脳の右半球の感情的混乱を抑えこむために、左半球から理性的なIFが生み出されるということもありません。
ただ、ひたすらパニックになり、PTSDのフラッシュバックを起こしながら、「安全基地」のない世界をひたすらさまよい歩くことになります。
このような状態に陥っているのが、境界性パーソナリティ障害(BPD)の人たちです。
境界性パーソナリティ障害(BPD)は、突然激しく怒りだしたり、見捨てられ不安がフラッシュバックしたりする一種のPTSDです。
BPDの人のキレる現象やフラッシュバックは、軽度の人格交代ですが、解離傾向が弱いため、別人格を形成するほどには至りません。
解離性障害の人が気配りに富み、心の中に大きな内的世界を抱え、多くの仲間を有しているのに対し、境界性パーソナリティ障害の人はカッとなりやすく、心の中は空虚で、一人ぼっちです。
解離傾向の強い人たちは、「逃走・闘争」反応に次いで、「固まり・麻痺」反応に至るので、感覚遮断することで、危機的状況から逃れて、冷静さを取り戻すことができます。
ところが、解離の弱い人たちは、ずっと「逃走・闘争」反応のままなので、常に危機的状況のまっただ中にいて、絶え間ない不安に苛まれて、冷静に考えることも、心が満たされることもありません。
解離による感覚遮断がうまくできず、敏感な心が常にむき出しの状態なので、傷つけ傷つけられながら、一人ぼっちで生きていくという苦しみに直面します。
解離が弱いBPDと、解離が強いIFやDIDの違いについては、詳しくは以下の記事をご覧ください。
![境界性パーソナリティ障害と解離性障害の7つの違い―リストカットだけでは診断できない | いつも空が見えるから]()
青年期のイマジナリーフレンドや、解離性同一性障害としての交代人格を持つ人たちも、それぞれストレスや苦悩を抱えているのは確かです。
しかし、助け手としてのイマジナリーフレンドにしても、身代わりとしての交代人格にしても、それらは耐え切れないストレスから身を守るための防衛反応、愛着トラウマというウイルスと戦う心の免疫系です。
もしも、心の免疫系が働かず、愛着トラウマに面しても、それらの別人格が生まれなかったなら、自分はどうなっていただろう、と考えたことがありますか。
世の中には、同じほどのストレスに直面しても、解離という防衛機制がうまく働かないせいで、苦しみを分け合う別人格を生み出せず、たった一人で立ち向かっていかなければならない人たちがいるのです。
IFがDIDになるとき
このセクションで考えてきたように、人格の多重化は、一種のスペクトラムのように連続した現象です。
単一人格 → PTSDやBPD(弱い解離) → IF(中程度の解離) → DID(強い解離)
解離の観点からIFを考察したこのセクション3の最後に、次の点を考えておくのは適切なことでしょう。
IFはいつかDIDに発展するのでしょうか。
一般的に言って、大半のIFはDIDに発展しないでしょう。
IFを持っている人は、むしろIFが存在することによって、解離性障害が発症するのを阻止し、心のバランスを保っているはずです。
そしておそらくは、人格の多重化と、人格交代は、別のメカニズムに基づいているのではないかと思われます。
先ほど解離とPTSDは正反対のものだと説明しましたが、人格の多重化は解離傾向によるものに、人格交代はPTSDのフラッシュバックの延長線上にあるように思われます。
したがって、解離傾向の強い人は人格が多重化し、PTSD傾向の強い人は感情がフラッシュバックし、解離傾向とPTSD傾向の両方が強い人が、多重化した人格のフラッシュバック、すなわち人格交代に至るのではないかと思います。
![PTSDと解離の10の違い―実は脳科学的には正反対のトラウマ反応だった | いつも空が見えるから]()
しかし、解離傾向のみ、PTSD傾向のみを持っているという人はまれで、たいていの人は程度の差こそあれ、どちらか一方が強いものの、もう一つの傾向も持ち合わせているでしょう。
かろうじてIFの存在によって心のバランスをとっている人が、より強いストレスに直面したとき、バランスが崩壊してDIDに発展する例は存在しているようです。
「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() によると、このセクションの最初で紹介したジキル博士とハイド氏は、当初はIFのような関係だったハイド氏が次第にコントロールできなくなり、DIDのような状態に発展していく物語でした。
によると、このセクションの最初で紹介したジキル博士とハイド氏は、当初はIFのような関係だったハイド氏が次第にコントロールできなくなり、DIDのような状態に発展していく物語でした。
ハイドは次第に彼のコントロールを離れて行動するようになってしまうのである。そしてジキルはハイドを「彼」と呼ぶようになり、もはや彼を「私」の一部とは感じなくなった。
ハイドはジキルとはまったくの別人格としてふるまうようになったのである。ハイドの出現によって保たれていた彼の心のバランスは、再び破壊に向かって突き進むことになってしまった。(p92)
ジキル博士とハイド氏は、単なる物語でありながら、もしかすると、作者のロバート・ルイス・スティーブンソンが経験していたことなのではないかと思わせるほど、 真に迫った描写がなされています。
スティーブンソンも作家たちの例に漏れず、愛着トラウマによる心の理論の強さを有していたのかもしれません。
大饗先生は、ジキル博士とハイド氏の崩壊の原因をこう指摘します。
つまり「解離」はある時期まではジキルにとって適応的に働いていたのである。
問題が生じたのは、そのような「解離」に頼っていた微妙なバランスが破綻した後であった。(p94)
そしてそれと同様の現象が、現実の臨床でも時おり見られると述べています。
アキナという人格は快活で奔放な性格であり、当初抑うつ的になりがちなナオミを「姉のように」励まし、ときには無気力に陥った彼女に成り代って(人格変換)、仕事を行ってくれることもあったという。
しかし、そのうちにアキナは夫に隠れて同僚のK氏との交際を始めるようになってしまった。(p97)
基本的にIFは、主人格を支える副次的な位置に存在しています。
IFがDIDに発展するような事態がそう簡単に起こるとは思えませんが、何かしらのストレスが異常に大きくなりすぎて、IFが自律性を持ち始めると、問題が複雑になってきます。
別人格が、主人格と苦しみをわかちあう仲間であるうちはいいのですが、主人格が危機に瀕して、別人格が身代わりや犠牲、盾となってかばうようになると、DIDへと発展していく可能性は否定できないでしょう。
先ほどの防衛反応でいうと、最初は「闘争・逃走」というPTSD的なシステムが働きますが、より大きな問題のもとでは、解離傾向の強い人の場合は「固まり・麻痺」に移行します。
これを日常生活に当てはめると、「固まり」、つまり感覚遮断して危機から逃れている段階では、IFは助け手として主人格を励ますことができます。
しかしさらにストレスが大きくなり、「麻痺」、つまり気絶して意識を失うという究極の手段を用いなければならなくなったら、日常生活においては、だれかが代わりに体をコントロールしなければならなくなります。
そのときこそ、耐え切れず意識の奥へと退いた主人格に代わって、IFが身代わりの交代人格となり、DIDへと発展してしまう瞬間なのかもしれません。
このセクションでは、夢や感覚遮断という解離の機能を通して、人格の多重化は防衛機制の強さによるスペクトラムであり、統合失調症のような病的なものではない、ということを見てきました。
最後の4つ目のセクションでは、ここまで取り上げたIFとは少し異なる特殊な例として、アスペルガー症候群のIFについて考えます。
第四章 「アスペルガー症候群」のもう一つのIF
これまで、IFが生まれる原因として、強い心の理論や、愛着トラウマ、解離という要因を考えてきました。
しかし、 ここまでの説明は、主に定型発達の人に当てはまるものです。
わたしたちの身近な別の民族とも称される、アスペルガー症候群などの自閉スペクトラム症(ASD)の人たちの場合、考え方そのものを見直さなくてはなりません。
IFに限らず、あらゆる物事において、違う尺度をもって考えなければ、彼らの独特な文化を理解することはできません。
興味深いことに、以前に記事で取り上げたとおり、アスペルガー症候群の人には、しばしばIFが見られることが報告されています。
![アスペルガーは想像上の友だちイマジナリーフレンド(IF)を持ちやすい? | いつも空が見えるから]()
ASDは解離症状を伴いやすい
アスペルガー症候群の人がIFを持ちやすい理由を簡潔に一言で言い表わせば、それはアスペルガー症候群の人は解離しやすいからだと思います。
「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() には、アスペルガー症候群の人がIFを持っているケースも紹介されていますが、アスペルガーは解離しやすいということがはっきりと書かれています。
には、アスペルガー症候群の人がIFを持っているケースも紹介されていますが、アスペルガーは解離しやすいということがはっきりと書かれています。
アスペルガーには解離様の現象が伴われることがまれではなく、それがチグハグな印象によりいっそう拍車をかけることがしばしばである。(p28)
セクション2で少し触れましたが、ある自閉圏の男性は、友だちとほとんど遊んだことがなく、周囲の家族の気持ちを読み取るどころかゲームに没頭して、青年期のIFを持つ人特有の内省的で柔軟な性格でもありませんでしたが、それでもIFを有していたと書かれています。
彼のIFはいったいどこから出てきたのでしょうか。IFは「心の理論」すなわち他の人への優れた感受性の結果、生み出されるものであるなら、共感性に乏しいと言われるアスペルガー症候群に見られるのはどうしてでしょうか。
哲学する赤ちゃん (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)では、そのような論理に基づいて、アスペルガー症候群を含め、自閉圏の子どもはIFを持たないと書かれています。
自閉症の子には空想の友だちがいないし、そもそもごっこ遊びをしません。ごっこ遊びとは何かということからして、わからないようです。
…自閉症の子どもは、他人の心の因果関係についての理論を組み立てるのに大変な苦労をしますし、いろいろな空想をして遊ぶこともありません。(p91)
しかし本当にそうでしょうか。
このような疑問について考えるに際し、導きとしたい言葉があります。
柴山雅俊先生は、解離の病理―自己・世界・時代![]() の中でこう述べています。
の中でこう述べています。
ASD者が解離症状を呈する割合は定型発達者に比べて若干多いという印象はある。
もちろん自己のあり方が異なるため、ASD者の示す解離が発症要因、症候、治療などさまざまな点で通常の定型発達者の解離とは違ってくるのは当然であろう。
定型発達者の解離のみが解離ではない。ASDにはASDの解離がある。(p181-182)
定型発達者の解離のみが解離ではなく、ASDにはASDの解離がある。言い換えれば、定型発達者のIFのみがIFではなく、アスペルガーにはアスペルガーのIFがあるのです。
![アスペルガーの解離と一般的な解離性障害の7つの違い―定型発達とは治療も異なる | いつも空が見えるから]()
ASDは「心の理論」が弱い?
まず最初のステップは、自閉症についてのさまざまな誤解を解くことです。
先ほどの説明において、アスペルガー症候群をはじめ、自閉症の人がイマジナリーフレンドを持たない根拠とされていたのは、心の理論が弱く、空想的な遊びもしない、ということでした。
これは、ローナ・ウィングが提唱した自閉症の三つ組の障害、すなわち、社会性の障害、コミュニケーションの障害、想像力の障害に基づいているのでしょう。
しかし、近年、自閉症の当事者研究や、注意深い調査において、三つ組の障害は必ずしも正しくないことがわかってきました。最新の診断基準のDSM-5でも、想像力の障害のような項目はなくなっています。
自閉症というと、他人に共感できず、気持ちがわからず、心の理論が弱い、空気の読めない人々だという未だ根強い偏見がありますが、成長し衰退する脳 (社会脳シリーズ)![]() では次のような研究が報告されています。
では次のような研究が報告されています。
過去の研究において、ASD児は他者の心情が理解できない、というように、二値論的に可-不可で考えられてきた。しかしながら、近年では、そのような二値論的な見方では理解できない実験結果もある。
…定型発達児では、最初から人物の感情に言及できていたものの、ASD圏内の子どもでは、当初人物の感情に言及せずに、情景や描かれている他の物などについて言及してしまった。
ASD圏内の子どもに対して、人物に注目するように追加の教示を行っていくと、彼らでも描かれた人物の感情を正答することができた。(p129)
この研究では、 ASDの子どもたちが、他人の心を理解できない、とされてきたのは誤りであり、単に注意が向かないだけなのだ、という見方が示されています。
すなわち、ASD児は自発的に他者そのものや、他者の顔、声といったものに注意が向きにくいということである。
…何よりも特筆すべきことは、他者に注意を向けられれば、感情や言外の意味といった従来難しいと言われてきた部分への理解も問題なく、かつ脳機能というレベルでも障害が認められなかったのである。(p130)
ASDの子どもたちは、他の人の感情を読めないのではなく、注意が向かないだけであって、適切な注意の喚起がなされると、感情や比喩も理解できたのです。
そのため、空気が読めなくなってしまうのは、ASDの生来の症状ではなく、自分から他人に関心を持ちにくく、コミュニケーションの機会が少なくなるので、結果的にコミュニケーションスキルが育ちにくいだけなのではないか、とされています。
そして、根本となっている他者に注意が向きにくいという特徴は、自他の区別があいまいなことによると推察されています。
また、発達障害の素顔 脳の発達と視覚形成からのアプローチ (ブルーバックス)![]() という本では、ASDの子どもは心の理論が弱い、と言われていることに関して、別の意見が提唱されています。
という本では、ASDの子どもは心の理論が弱い、と言われていることに関して、別の意見が提唱されています。
誤信念課題に関するもうひとつの批判は、そもそも一定の割合で自閉症児が「心の理論」の課題をパスしてしまうという事実にある。バロン=コーエンらの研究にしても、約2割の自閉症は課題をクリアしていた。
…誤信念課題の成績がよい(他者の心がよめる)自閉症児はほど理解できた物語の数は多く、社会性に問題のない、知的障害児や健常児とほとんど差がなかった。(p26-27)
この誤信念課題というのは、サリーとアンのテストのような、他人の立場に立って考える能力を測る、心の理論の発達を調べるものです。
一般にASDの子どもたちは、サリーアン課題がうまくできないので、心の理論が発達しておらず、他者の気持ちも読めない、と言われがちなのですが、そもそもASDの子どもの2割はこのテストを通過し、他の人の気持ちを適切に理解することができます。
さらに、誤答してしまう残りの8割のASDの子どもたちの場合も、性急に心の理論が育っていないと結論するのは間違っている可能性が示唆されています。
誤った解答をした場合でも、その理由を問われると、きちんと心にかかわる用語を駆使して説明をする。
…つまり「誤信念課題」にパスできなかったとしても、自閉症児は相手の心を推測することはできるのである。
パスできない問題の原因は、その推測が普通とは異なる独自の視点に基づくということだ。(p27)
ポイントは、心の理論がないことではなく、心の理論が定型発達者とは異なる、という部分にあります。
定型発達の心の理論のみが心の理論ではなく、ASDにはASDの心の理論があるのです。
そのことをまざまざと示しているのが、ASDの人はASDの人同士であれば、強く共感し、互いの気持ちを深く理解し合えるということです。
![アスペルガーは「共感性がない」わけではない―実は定型発達者も同じだった | いつも空が見えるから]()
わかってみれば簡単な話で、定型発達の人たちには定型発達の心の理論があり、ASDの人にはASDなりの心の理論があるので、どちらも自分と同じ集団の人の気持ちはわかるのに、自分とは違う集団の人の気持ちは理解できないのです。
もしASDの人が多数派で、ASDの人の心の理論が一般的だったとしたら、今ごろ定型発達の人たちは、心の理論が欠如していると言われているかもしれません。
そうすると、ASDの人たちは他者の気持ちを考えることができないから、イマジナリーフレンドも持たない、とする論理は成り立たなくなります。
確かに、定型発達者のIFとは性質は異なるはずですが、ASDの人はASDなりのIFを持っているとしても何ら不思議ではありません。
また、ASDの子どもは空想的な遊びをしない、とも言われていましたが、それはあくまでも定型発達の子どもがするようなごっこ遊びなどをしないというだけで、実際にはASDの子どもも様々に想像力を働かせている、ということは、当事者のニキ・リンコさんの自閉っ子におけるモンダイな想像力![]() を読めばわかります。
を読めばわかります。
アスペルガー症候群だったとされる、ルイス・キャロルやハンス・クリスチャン・アンデルセンの作品を読むと、ASDの人でも豊かな空想世界や、登場人物を思い描ける場合があることは明らかです。
![自閉症・アスペルガー症候群の作家・小説家・詩人の9つの特徴 | いつも空が見えるから]()
定型発達者の人が読むと、キャロルやアンデルセンの童話の登場人物は、どことなく異質で奇妙な人たちに思えるでしょう。
それは、彼らが創りだした登場人物たちが、定型発達者の心の理論ではなく、ASDの心の理論に沿って行動する人たちだからです。
心の理論が強くなると、小説家としての才能や過剰同調性につながると述べましたが、アスペルガーの場合も、キャロルやアンデルセンのように小説家になる人がいますし、さらには過剰同調性になる場合もあることがわかっています。
それで、アスペルガー症候群などASDの人たちが、IFを持ちやすいかというと、特に定型発達に比べて多いわけではないかもしれませんが、IFを持たないというわけでもないのでしょう。
アスペルガーは中心不在
ASDにはASDの心の理論があるのであれば、ASDが持つIFの特徴は、定型発達の人たちのIFと異なるのでしょうか。
その可能性は十分にあります。
ASDの人たちは、先ほど少し触れたように、自他の区別に困難を抱えやすいようで、まとまったアイデンティティを持たないことが少なくありません。
大饗先生は、「豹変する心」の現象学―精神科臨床の現場から![]() の中でその理由をこう説明しています。
の中でその理由をこう説明しています。
イマジナリーコンパニオンとは中心を失った人格モードの乱立を意味していた。
あるいはアスペルガー症候群においては、そもそも主体の一貫性、すなわち過去-現在-未来という階層が成立せず、エピソードがランダムに乱立してしまうことが問題になっていた。(p210)
ASDの人たちは、時間の連続性の感覚があいまいであり、過去から未来へと脈々と続く一つの自分というのをイメージしにくいようです。
これは、ASDの人が感覚統合の問題を抱えていて、運動時に手足などを協調して動かすことが苦手だったり、複数の五感からの入力を統合するのが難しかったり、時には空気に溶け込むような拡散体験を訴えたりすることと共通しています。
一つのまとまった自己を持ちにくいASDの人たちは、しばしば、生きるためにIFやDIDのようなしくみを活用することがあります。
解離の病理―自己・世界・時代![]() の中で、広沢正孝先生はこう述べています。
の中で、広沢正孝先生はこう述べています。
彼らは一般者のように、固有の自己像を持ち、「自生的に人格の中心から出発し、種々の外的な状況にふさわしい反応を」取ることは困難である。
これに対処するために彼らは、しばしば内界にモデルとなる人物像を取り入れて、それにピッタリ合わせる形で生きようとすることもある。(p71)
この説明によると、ASDの人たちは、新しいことに対処する際、柔軟に適応する代わりに、それにふさわしい人格を取り入れて、あたかも服を着替えるように、それぞれの人格になりきることで対応する場合があります。
さらに彼らの中にはこのような、外部の人物像ではなく、自らのうちに具体的な人物像を創造し、それにピッタリ合わせる形で生きようとする者もある。それはとりわけ年少者の女性に多いように思われる。(p71)
そのような衣服を着替えるかのような人格の多重化は、外部の人物像を取り込むだけでなく、自分で創造することによって生まれる場合もあります。
自分で人格を創れるということは、当然IFを創ることもできる、ということにほかなりません。
ここでは特に年少者の女性のASDにそのようなケースが多いとされています。女性のASDは男性のASDに比べて空気が読めない傾向は弱いので、IFを生み出しやすいのかもしれません。
![女性のアスペルガー症候群の意外な10の特徴―慢性疲労や感覚過敏,解離,男性的な考え方など | いつも空が見えるから]()
この後の文脈では、その一例として、自閉症だったわたしへ (新潮文庫)![]() の著者ドナ・ウィリアムズが挙げられています。
の著者ドナ・ウィリアムズが挙げられています。
ドナは、ウィリーとキャロルという別人格を創造することで、学校や人間関係の問題に対処していました。
ドナはウィリーとキャロルという別人格の存在を認識していましたし、記憶もつながっていましたから、古い診断基準に当てはめると、ドナはジキル博士と同じく、DIDではなくIC、つまりイマジナリーフレンドを持っていたとみなされるはずです。
広沢先生は、ASDの人たちにとって、このような多重人格的な生き方はごく自然なものだとさえ述べています。
PDD型自己の場合、そもそもの構造が区画化されており、「個」の感覚が希薄である。
したがって高機能PDD者においては、むしろいくつかの人物像が併存することは自然なことといえよう。 (p72)
PDDというのは広汎性発達障害のことで、現在はASDの一部としてまとめらたものです。そのようなPDD、つまりASDの人たちは中心となる自己のアイデンティティが希薄なために、その場その場で様々な人格になりきることは、トラウマへの反応ではなく、むしろ日常の一部なのです。
とはいえ、ASDの人たちは、愛着形成に遅れが生じやすいと言われていますし、孤立しがちでトラウマ経験にさらされることもあります。
ですから、単にASDだから人格の多重化が生じるというわけではなく、愛着トラウマなどの様々な要因が重なり合っているケースも少なくないでしょう。
定型発達のIFとASDのIFの違い
では、定型発達の人たちが持つIFと、ASDの人たちが持つIFに、質的な違いはあるのでしょうか。
まず、脱ぎ着する衣服のようなIFは、どちらかというとASDに特有のものであり、定型発達の人のIFは人格交代のために創られることは少ないのではないかと思います。
しかしダニエル・タメットのIFのアンのように、ASDの人がただ会話するためのIFを生み出すことももちろんありますし、定型発達のIFがときに人格交代して主人格を手助けすることもあるでしょう。
また、IFを持つ年齢でいえば、ASDの子どもは発達が遅れるため、幼児期ではなく、学童期などの遅い時期にIFを持ちやすい可能性があります。
しかし、ドナ・ウィリアムズのウィリーは2歳のころ、キャロルはその1年半後に現れたので、定型発達の子どもと変わらない可能性もあります。
興味深いことに、広沢先生は、先ほどの引用文の続きで、次のように述べています。
また彼らの場合、このような複数の人物像の存在を、ごく自然に認識しており、むしろうまくそれらを使いわけることが、社会適応の手段となっている。
一方一般型自己をもつ解離性同一性障害の患者にとっては、…最終的には「個」の統一が課題となってくる。複数の人格の存在自体が苦痛となり得る。(p72)
ASDの人は中心不在のため人格の多重化を自然なものと感じるのに対し、定型発達のDIDの人は、なまじ中心となる自己が存在するせいで、人格の多重化を苦痛に感じる、と書かれています。
この違いは興味深いものですが、必ずしもASDと定型発達の感じ方の違いとはいえないようです。
というのは、以前も登場した、アリソンの提唱する多重人格障害(MPD)、つまり7歳以前に発症した多重人格の人の感じ方は、ASDの人の感じ方とよく似ているからです。
アリソンは「私」が、私でない人たち―「多重人格」専門医の診察室から![]() の中で、7歳以前に多重人格となった人は、自己が確立する前に人格が多重化し、本来の自己は内側に隠れてしまったために、自己同一性の葛藤を感じないので「解離性同一性障害」ではなく「多重人格障害」の名称のほうが適切だと述べています。(p259)
の中で、7歳以前に多重人格となった人は、自己が確立する前に人格が多重化し、本来の自己は内側に隠れてしまったために、自己同一性の葛藤を感じないので「解離性同一性障害」ではなく「多重人格障害」の名称のほうが適切だと述べています。(p259)
アリソンの主張するMPDの人たちは、自己同一性の違和感を感じないだけでなく、場面ごとにふさわしい人格を創りだして対処することが当たり前になっていて、ASDの人が複数の人格を脱ぎ着して現実に対処する姿とよく似ています。
MPDの人たちの大半は、もともと自閉的なわけではないでしょうが、自己が確立する前に人格の多重化が生じてしまい、中心となる自己の不在という点でASDに似るため、同じような生き方に至りやすいのかもしれません。
しかし、ASDか定型発達かを問わず、IFやDIDなどの人格の多重化を抱える人の中には、自己同一性の葛藤を抱える人たちと、まったく自然なこととみなして違和感を感じない人たちとがいる、という点は注目に値します。
IFにも当事者研究が必要
このセクションを締めくくるにあたり、自閉スペクトラム症(ASD)の人たちと、青年期のIFを抱え持つ人たちとが、文化的な意味において、同じような局面に立たされているという共通性を考えたいと思います。
自閉スペクトラム症は、その名の通り、程度の軽いものから重いものまで、スペクトラムとしての連続性をもっている、ということを先に述べました。
単純に白か黒かで二分できれば楽なのですが、定型発達とカナー型の自閉症という両極端の人たちが比較される一方で、その中間に位置するアスペルガー症候群の人たちは、社会からも医学者からも長年誤解されてきました。
近年、ようやくアスペルガー症候群の当事者自身が、自伝や当事者研究を通して、自分たちは何者なのかを自ら語るようになり、心の理論がないとか共感性に乏しいといった偏見が正されてきたように思います。その中には、先ほどから名前が出ている、ドナ・ウィリアムズやダニエル・タメットも含まれています。
イマジナリーフレンドのような人格の多重化も自閉症と類似したスペクトラム性を持っている、ということを説明してきましたが、こちらもやはり、極端な例のDIDは研究されてきたものの、DIDと単一人格者の中間に位置する、青年期のイマジナリーフレンドの事例は、ほとんど手がつけられてきませんでした。
そのせいで、イマジナリーフレンドを持つ青年は、精神的に病んでいるとか、妄想の世界に引きこもっているといった誤ったイメージが流布しているように思えます。
こうした誤解が解かれるためにはアスペルガー症候群の人たちが、自分たちの口でそのユニークな文化を語り始めたように、青年期のIFを持つ人たち自身が、当事者研究を通して、その独特な文化や世界観を発信しなければならないのではないでしょうか。
子どものイマジナリーフレンドを研究してきた麻生武先生は、想像の遊び友達一その多様性と現実性の最後にこんな付記を添えていました。
日本では,「想像の遊び友達」について語られることがほとんどなく,研究されることもほとんどなかった。
よって,日本において「想像の遊び友達」を持っていた人々・子どもたちは,そっと人知れず自分だけの王国を持っていたと言える。
私は,その王国に足を踏みいれ,その高原に咲く草花を分類しこのような形で発表してしまった。
本論を読んでくださった方が,子どもたちの内なる王国を,好奇心という土足で踏みにじらないことを願いたい。
とは言え,このように発表しつつそのような願いを人にすること自体あまりにも自己中心的かとも思っている。
アメリカが発見されなければ,1千万のインディアンが殺されずにすんだのにという思いがある。私の発見したと思っている王国がアメリカではないことを祈りたい。
何度読んでも、非常にすばらしい心遣いが感じられる文章だと思います。
イマジナリーフレンドという概念についての記事がネット上に増えるにつれ、はじめは、良い意図で書かれていたとしても、分母の拡大ととも底質な意見を述べる非当事者が増えることは避けられないでしょう。
非当事者は、決して当事者の感覚を十分正しく把握することはできませんから、誤った見解が流布すことになります。
しかし、今はアメリカ・インディアンが虐殺された時代とは違うのです。アメリカ・インディアンは、自ら声を上げる場を持っていませんでしたが、現代社会は、インターネット上を含め、当事者たちが自分の言葉を発信する機会が多くあります。
確かに、IFを持つのが子どもだけであれば、当事者研究の余地はなかったかもしれません。しかし実際には、青年期以降もIFは存在するのであり、子どものIFとはある程度地続きになっているため、当事者研究の余地は大いにあると思います。
もちろん、IFを持つ人の中にはIFの存在を発信することに違和感を持たない人がいる一方で、IFの存在を秘しておきたいと感じる人もいるでしょう。
IFが一人の人間としての人格を持っている存在であることを考えると、いち早く当事者研究を世に送り出したここにいないと言わないで ―イマジナリーフレンドと生きるための存在証明―の著者のように、友だちの存在を積極的に語りたい人がいる一方で、私秘性を保ち、プライバシーを守りたいと考える人がいるのも当然です。
走馬灯などの解離体験の不思議について記しているなぜ年をとると時間の経つのが速くなるのか 記憶と時間の心理学![]() の中に、「意識は座席が一つしかない劇場」であると書かれているとおり、どれほどの言葉を持ってしても、IFを持つ人の実感を持たざる人に伝えるのは難しいことです。(p335)
の中に、「意識は座席が一つしかない劇場」であると書かれているとおり、どれほどの言葉を持ってしても、IFを持つ人の実感を持たざる人に伝えるのは難しいことです。(p335)
自分だけが感じているIFという不思議な現象のクオリアを言葉にしてしまうと、多くの重要な要素が削ぎ落とされてしまい、感動が失われるように感じる人もいるかもしれません。
IFはいわば、起きながらにして夢を見ているような現象だとセクション3で説明しましたが、夢は夢のままでそっとしておきたい、まだ現実に目覚めることなく、自分だけの劇場で夢の続きを見ていたいと感じる人もいることでしょう。
様々な感じ方があるでしょうから、他の人の気持ちを尊重するのは大切なことです。
しかし、もしも、アスペルガー症候群の当事者研究のように、当事者として、自らの手でIFの体験談としての半生記や、系統立った文化論をまとめたい、と感じる人がいるとすれば、それはきっと意義のある仕事になると思うのです。
終章 あなたのIFは、あなただけのIF
以上が今回のさらなる4つの考察のすべてです。
この記事で考えたことを最後にまとめましょう。
まず、一つ目のセクションでは、IFは「心の理論」を基盤として、他の人の気持ちを想像する能力から生じることを説明しました。
「心の理論」が発達した子どもが「いない人」のことまで考えてしまうように、小説家もまた強い感受性によって、架空の登場人物を創作することができました。
二つ目のセクションでは、「心の理論」が強く発達しすぎる背景として、「愛着トラウマ」の存在を考えました。
生後わずかな期間の経験が、脳の左右の結びつきを弱め、「安全基地」としてのIFを生み出すことがあります。
三つ目のセクションでは、「解離」という脳の機能の正体に迫りました。
それは感覚遮断によって、起きながらにして夢を見ているような不思議な状態を創りだすものであり、解離による人格の多重化は病気ではなく愛着トラウマに対する防衛反応である、という点を明らかにしました。
最後の四つ目のセクションでは、「自閉スペクトラム症」のIFの特殊性について考えました。
一般的な意見とは異なり、自閉スペクトラム症の人たちも彼らなりのIFを持つことがあり、複数の人格を抱え持つ生き方を自然なものと感じているのです。
これら今回の4つの考察が目的としていたのは、子どものIF、青年期以降のIF、そしてDIDの交代人格、さらにはアスペルガー症候群のIFという、それぞれ一見隔たっているように感じる現象を結び合わせることでした。
様々な違いはあるにせよ、根底のところでスペクトラム性を有している、ということをある程度、論理的に説明できたのではないかと思います。
しかし、このようなスペクトラム性を有しているとはいえ、最後に、強調しておきたいのは、あなたのIFは、あなただけのIFである、ということです。
IFは現実の人間と同じように、一人ひとり性質が異なります。この記事に書いたような一般化された内容がぴったり当てはまるというのはむしろ稀で、実情はもっと多様性に富んでいるはずです。
わたしの見解としては、IFというのは、意識して創り出せるものではなく、ある意味で生まれつきの才能に近いものなのではないかと考えています。
正確には生まれつきではなく、生まれて間もない愛着形成の時期に、その人の脳の解離傾向が決定されます。その時期を過ぎると愛着形成が難しくなるように、後になって解離傾向を強めたり弱めたりすることはおそらく不可能です。
それは、解離傾向が比較的弱いため、ストレスに直面しても、IFを創りだすことができず、心の中が空っぽのまま、さまようことになる境界性パーソナリティ障害の人たちの場合によく表れています。
岡野憲一郎先生は、解離新時代―脳科学,愛着,精神分析との融合![]() の中でこんなことを綴っていました。
の中でこんなことを綴っていました。
私自身は会ったことがないが、解離に興味を持ち、「そのような症状を持ってみたい」という願望や空想を持つ人は少なからずいるということを、患者さんたちから聞くことがある。
私は「解離になりたいと思っても簡単にはなれない」という立場である。「解離になりたい」人たちは「解離になりたい」けれどもそうなれない人のはずだ。(p5)
なぜなのかよくわかりませんが、世の中には「解離になりたい」と考える人たちが存在するようです。
アインシュタインのようなアスペルガー症候群の天才の論理的な思考に憧れて「アスペルガー症候群になりたい」と考える人たちと似ているかもしれません。
実際に、以前の記事で取り上げたように、IFの作り方を知りたい、と思って調べる人たちはけっこういるようです。
![イマジナリーフレンドは自分で「作る」ものなのか「作り方」があるのか | いつも空が見えるから]()
しかし、岡野先生は『「解離になりたい」人は「解離になりたい」けれどもそうなれない人のはずだ』と述べています。
わたしもまったくの同意見で、上記の記事で説明したとおり、たとえIFを作りたいと思って作った人がいるとしても、生来の解離傾向によって創りだされたIFと、見よう見まねで創ったIFとでは、母語と第二言語ほどの違いがあるはずです。ネイティブになりたいと思っても簡単にはなれないのです。
2015年の第14回日本トラウマティック・ストレス学会で発表された、大饗広之先生らの近年の研究、大学生年代におけるイマジナリー・コンパニオン体験の諸相 - を見ても、解離群と非解離群のIF周辺体験を比較したところ、性質が大きく異なることがわかっています。
実際に、この記事をここまで読んでくださった方であれば、IFが単なる空想によって生まれるわけではないことを承知しておられると思います。
それは幼少期からの愛着トラウマや過剰同調性、あるいはアスペルガー症候群などからくる苦悩と絶えず向き合わなければならなかった結果、防衛機制が創りだした助け手であり、闇夜にきらめく星のように、まず深い漆黒があって始めて輝き出すものなのです。
上記の記事で取り上げたタメットらのように、IFを自分で創った、と感じている人もいるかもしれませんが、厳密な意味でIFらしいIFを創れるのは、おそらくはある程度の潜在的な解離傾向を持っている人たちに限られるのでしょう。
幼いころに決まる解離傾向を、後々手に入れることができない、解離になりたくてもなれない、というのは、裏を返せば、解離をやめたくてもやめることはできない、という意味でもあります。
解離性障害の人は、加齢と共に症状が軽くなりますし、人格の多重化が消えていくこともありますが、それは生来の解離傾向が弱まったという意味ではなく、解離を用いなくてもストレスに対処できるようになっていくということでしょう。
DIDの予後についての次の記述は、生来の解離傾向が、おそらく生涯にわたりそれほど変化しないことを裏づけているように思えます。
DIDを持つ患者のかなりの部分は、大きなストレスがない保護的な環境に置かれれば、次第に人格部分の出現がみられなくなり、「自然治癒」に近い経路をたどることが観察される。
…ただしそのような例でも多くが長年にわたし心の中に人格部分の存在を内側で感じ続けたり、時折幻聴を体験したりすることが報告されている。(p139)
たとえ別人格が役目を眠りにつこうとも、それらは「眠る」のであって「消える」わけではないようです。それらが本当の意味で「消える」のは、主人格が死ぬときでしょう。
IFにしても、DIDの交代人格にしても、ひとたび精緻な人格としてのアイデンティティを形成したなら、生涯にわたって主人格と人生を共にするのでしょう。
解離傾向は、コントロールを失うと、ときに苦痛を伴うものとなるかもしれませんが、基本的には、苦痛の原因は愛着トラウマなどの別の部分にあり、解離傾向は、それらから心を守るために働いています。
あなたの解離傾向は、優れた感受性や内省的な思考力、芸術的才能などをもたらしているかもしれませんが、それらすべてはあなただけのものです。それを後から獲得することはできません。
それはすなわち、あなたが出会ったIFは、だれか他の人が創り出したいと思っても、決して創り出すことができず、あなたのために、ただあなただけのために、オーダーメイドの存在として、生み出されたものだということです。
最後に、もう一度言います。
あなたのIFは、あなただけのIFなのです。
アリソン・ゴプニック 亜紀書房 2010-10-27
 激しい気分の浮き沈みや慢性的なうつ状態、幻覚、対人関係の不安定さや依存症。
激しい気分の浮き沈みや慢性的なうつ状態、幻覚、対人関係の不安定さや依存症。という本を参考にまとめてみました。
は、虐待など、子ども時代の慢性的なトラウマ経験を抱えた子どもたちを治療してきた専門家10人による、トラウマの影響や治療についての解説書です。
には、アタッチメント障害(愛着障害)などのもっと詳しい説明や、自我状態療法やトラウマフォーカスト認知行動療法といった特殊な治療法の具体例なども載せられているので、関心のある人は読んでみてください。